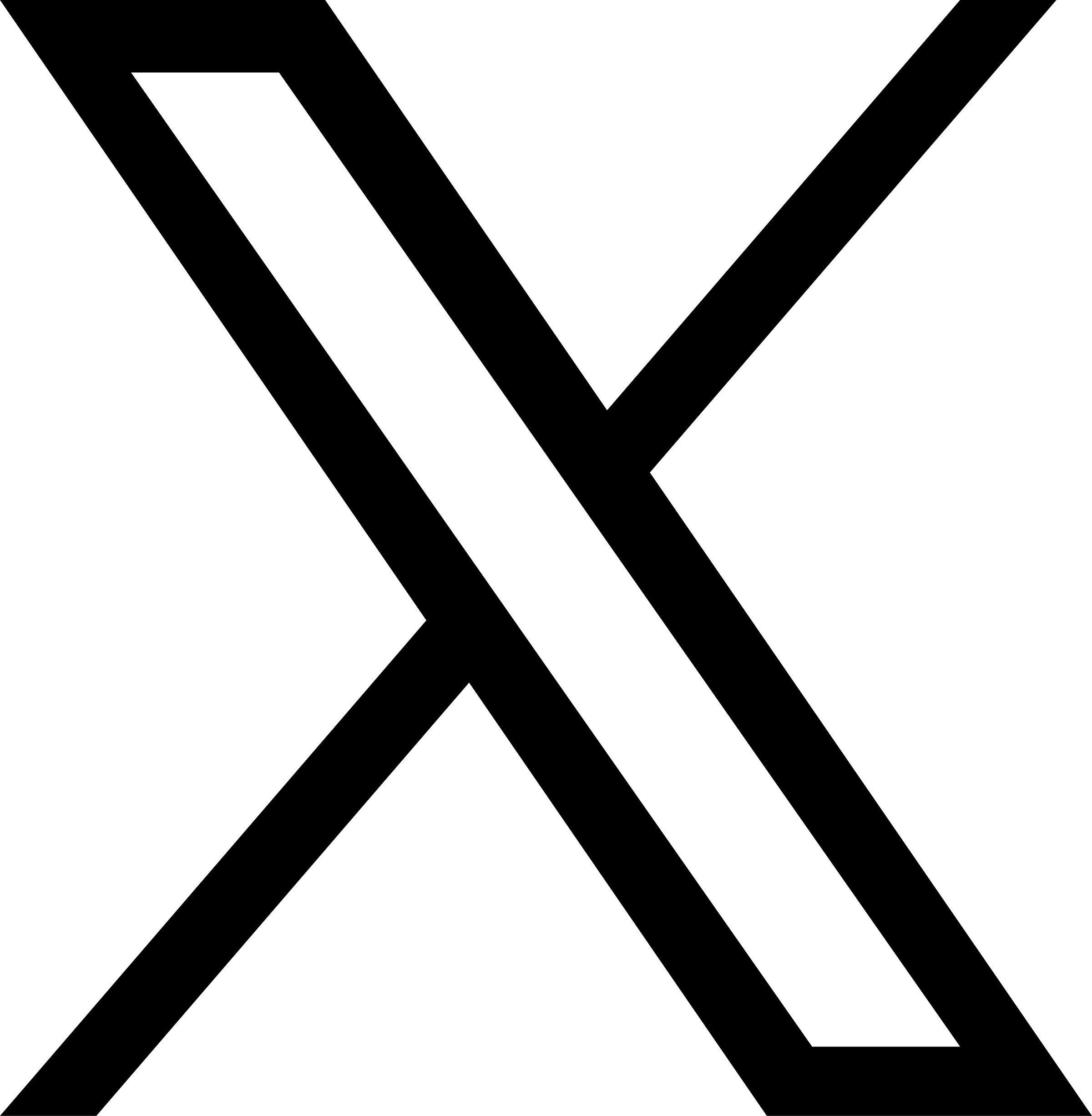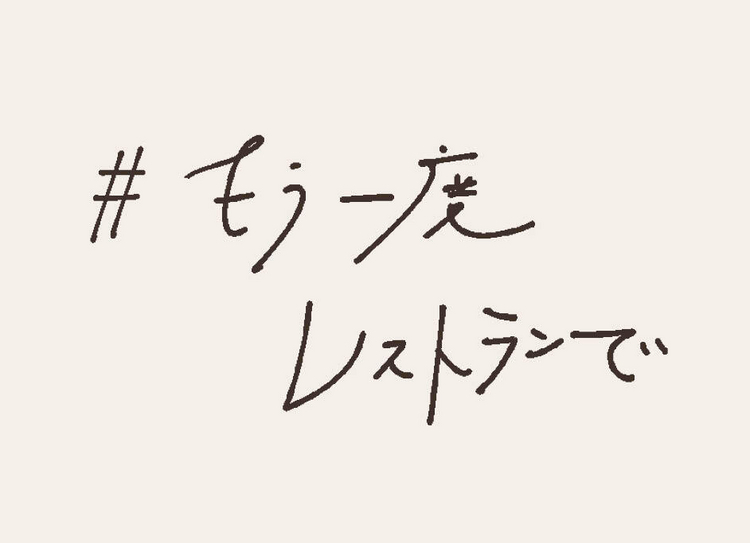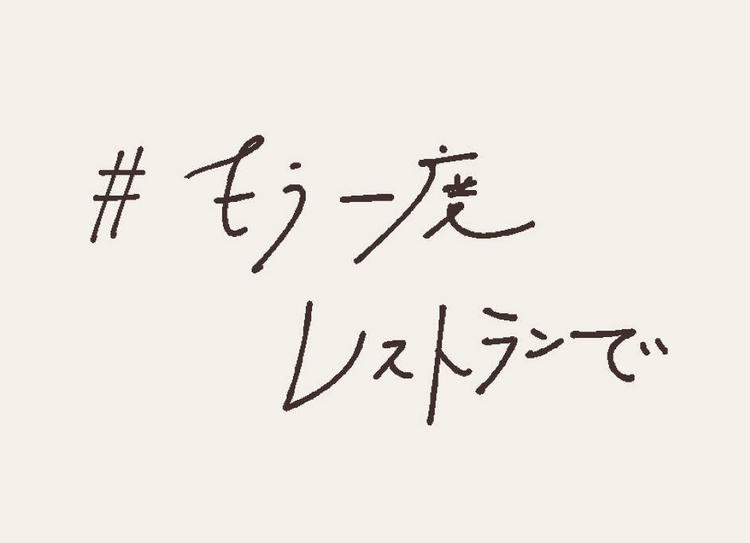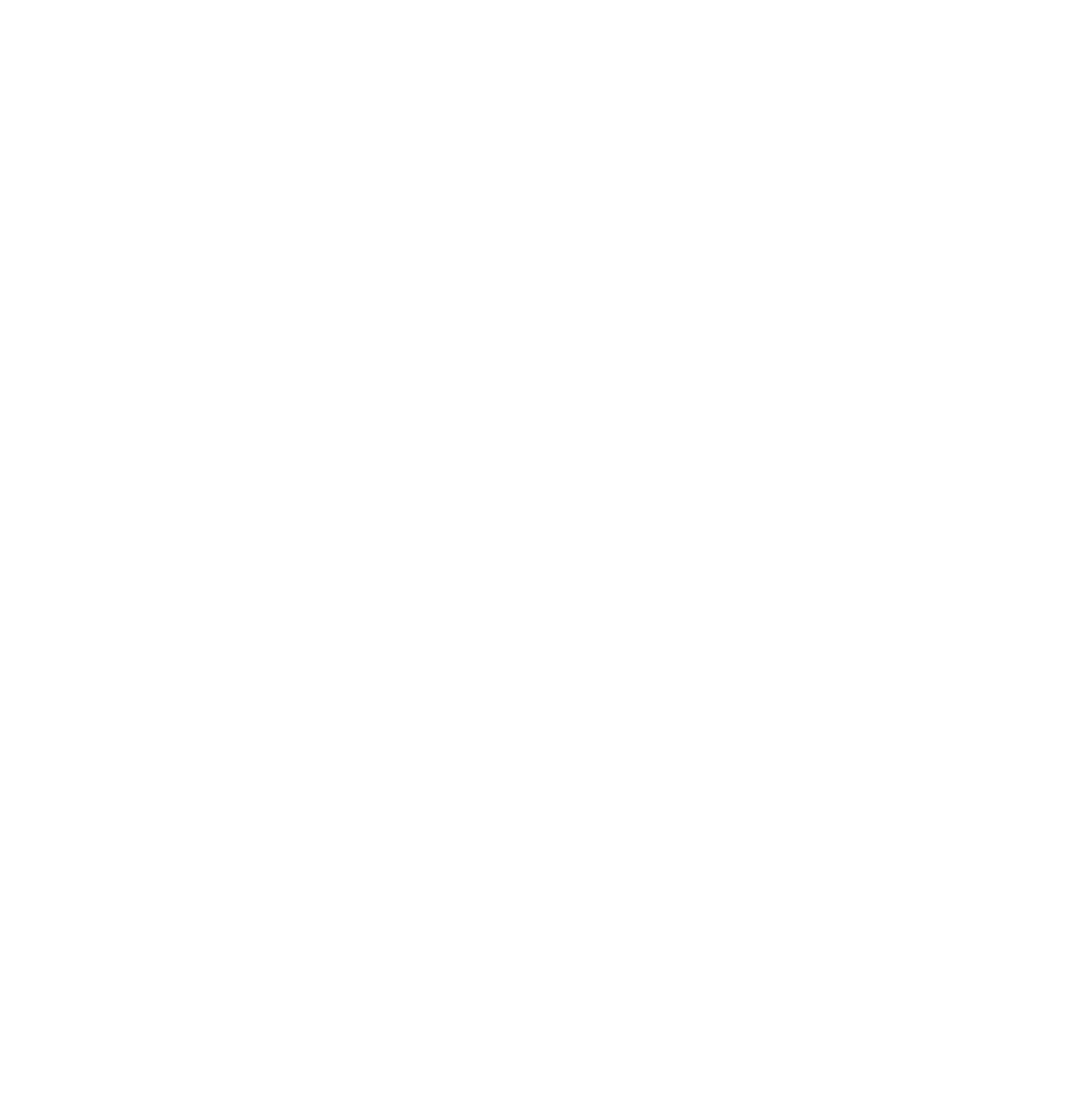<連載短編小説>#もう一度レストランで|「白い皿に一輪」東直子
恋人未満の二人をあとおしし、家族の記念日をともに祝い、おいしいお酒に友だちと笑う。レストランでのありふれた光景が、特別なものだったと気づいたこの数年。レストランは食事をするだけの場所ではなく、人と人とが交わり、人生が動く場所だった。これは、どこにでもあるレストランで起こる、そんな物語のひとつ。

十分前に着いたのに、彼女はもうそこにいた。こげ茶色のテーブルの上に白い顔を浮かべている。私をみとめて軽く片手を上げた。私も応えるように右手をあげて、少し言葉を探してから「ひさしぶり」と言った。彼女は微笑んだ。まぶしそうな目をして「お久しぶりです」と、頭を少し下げた。彼女の背後の壁に水牛の角のオブジェが飾られているのに気がついた。
彼女——宮下さんに初めて会ったのは、五年ほど前だ。カルチャーセンターのフラワーアレンジメント講座を一緒に受けていた。土曜日の午後の講座で、終わったあとに何人かでカフェに移動して話をすることもあった。お茶を飲み、甘いケーキを口にとかしつつ連絡先を交換した一人が宮下さんだった。色が白くて控えめな人という印象しか持っていなかった。
フラワーアレンジメント講座が終了しても、連絡先を交換したメンバーとは、数ヶ月に一度くらいはレストランを予約して会食をした。最初の二、三回は宮下さんもいたが、あるときからなぜか来なくなった。
そのうちに新型コロナウイルスの感染が拡大してきて、食事会自体もなくなった。もうあのメンバーと会うこともないのだろうな、とぼんやりと思っていたころ、宮下さんから、ランチでもしませんか、というメールが突然届いたのだった。
なぜ、今、私に……? 正直とまどったが、好奇心の方が勝り、会うことにしたのだ。
「ごめんなさいね、急に呼び出したりして。お忙しいのに」
「いえいえ、ぜんぜん、いつも土曜日は何もすることがなくてもてあましてたから、声をかけてもらって、うれしかったです。このお店、よく来られるんですか?」
「ええ、まあ、ときどき……」
宮下さんは、はにかんだような笑顔を浮かべて少しうつむいてまばたきをした。
「それで、その……」
上目遣いで宮下さんが言うので、何か相談ごとでもあるのかと身構えた。
「トマトのサラダ、頼んでもいいですか?」
「え、あ、トマト、ええ、はい、もちろん!」
水牛の角が壁に飾ってあるこの店は、一九五〇年代のアメリカを彷彿させるようなレトロな雰囲気のカジュアルなカフェで、メニューの「前菜」の項目の中の三番目に、その「トマトのサラダ」は記載されていた。「トマトのサラダ」の他に、私はほうれん草と鮭のクリームソースのスパゲッティーを、宮下さんはしらすと菜の花のショートパスタを注文した。
最初に運ばれてきた「トマトのサラダ」を見て、私は軽く、あ、と声が出た。
「薔薇……」
薄切りのトマトが花びらのように重ねられ、白い皿の上に大輪の赤い薔薇を咲かせていた。幾重にも重なるみずみずしい花びらに、オリーブオイルが細い糸のようにかかり、淡く光っている。朝露をまとっているよう。
「きれい……」
私が関心して声に出すと、宮下さんがにっこりと満足そうに笑った。
「ね、トマトの薔薇。ここでこれが出てくるのって、ちょっと意外でしょ。だから、見てもらいたくて」
「わあ、なんか、うれしいです。ありがとうございます」
「いやいや、私が作ったわけじゃないから」
宮下さんは、顔の前で白い手をひらひらさせた。
「私、あのとき、渾身のブーケを自分で作ってみたくて、フラワーアレンジメントの教室に通ったんですよ」
「ブーケって、花嫁さんの? もしかして、ご自分の?」
「はい、でも、それ、なくなっちゃったから……」
少し淋しそうに笑って、宮下さんは赤い薔薇のひとひらを口に運んだ。
「なくなった」というのは、コロナで結婚式が中止になったのだろうか。それとも、結婚自体が流れたのか……。どっちですか? なんて訊けないので、「そうですか……それは、残念でしたね」と小さな声で言った。
宮下さんは顔をあげてにっこりと「はい」とだけ言った。それ以上は聞いてくれるな、という意味の笑顔のような気がして「お気持ち分かります」という言葉の代わりに軽く相槌を打った。
「でも、花に向き合っていた時間は楽しかった。お花をさわることが好きな人たちが、同じ時間、同じ場所にいるって、なんか、いいなって」
「そうですね」
しみじみと同意した。花をどのように配置すれば映えるか、かっこよくなるかということにみんな集中していた。作業に没頭していると、他のすべての事を忘れられた。つかの間の非日常に浸って自分の美しいと感じる小世界を作り上げる、希有な時間だったと思う。
「あなたの活けたお花、誰よりも独創的でした」
宮下さんが大きな瞳をまっすぐこちらに向けて言った。
「え、私の、お花が?」
「ええ、赤い薔薇を一本だけ高くした作品を作ったときがあったでしょう。あれ、好きだった」
「あ、ありがとうございます。あれ、先生の評価は低かったですけど」
「私は好きでした。だから一緒に、これを」
宮下さんが、トマトの花びらの一枚をフォークでさくりと刺した。

その後届いたそれぞれのパスタを食べ終えたあと、私はプリン、宮下さんはカシスのシャーベットをデザートに注文した。最後に紅茶をたっぷり飲んで私たちは別れた。
ずっとたわいのない事を話しただけで、特に用事があったわけではなさそうだった。宮下さんはどうやら、本当にあのトマトのサラダの薔薇を見せたいがために私を呼び出したようだった。
おもしろい人だと思う。そして、そういうことを私が喜ぶと思ってくれたことがなんだか嬉しかった。宮下さんに、私だったら何を見せてあげたいかなあ、と帰り道で考えていた。
著者プロフィール
-

-
東直子(ひがし・なおこ)
歌人、作家。1996年、第7回歌壇賞、2016年、小説『いとの森の家』で第31回坪田譲治文学賞受賞。歌集『春原さんのリコーダー』『青卵』、小説『とりつくしま』『階段にパレット』、入門書『短歌の詰め合わせ』、エッセー集『千年ごはん』『愛のうた』、穂村弘との共著に『短歌遠足帖』など。最新刊は『短歌の時間』。2022年、原作の短歌を担当した映画『春原さんのうた』(杉田協士監督)上映。Paraviで「共感百景」(解説)配信。

イラストレーションの講座を受けていたときに、よく利用していました。本屋さんの側のひっそりとした空間で、キッシュなど食べながら受講生同志でたわいない話をしました。
この記事を作った人
文/東 直子 イラスト/yasuna 構成/宿坊 アカリ(ヒトサラ編集部) 企画/郡司しう
-

東京都グルメラボ
ランチもディナーも愛犬と一緒に楽しめる! ペット可のカフェ&レストラン|東京
-

東京都グルメラボ
外の景色を眺めながら食事を楽しめる、テラス席のあるお店5選|東京
-

東京都グルメラボ
お一人様歓迎! 一人でも立ち寄りやすいお店5選|東京
-

東京都グルメラボ
開放感あふれるテラス席で食事を楽しめる東京のお店5選|東京
-

山形県旅グルメ グルメラボ
山形を訪れたら行きたい、地元食材が味わえるお店5選|山形
-

沖縄県旅グルメ
沖縄・那覇のメインストリート「国際通り」を訪れた後に立ち寄りたい島料理のお店5選|沖縄
-

函館旅グルメ
異国情緒や歴史を感じる北海道の観光地・函館を訪れた際に立ち寄りたいお店|北海道
-

川崎グルメラボ
神奈川県「川崎」エリアで個室がある、普段使いできるお店|神奈川
-

北海道旅グルメ
北海道・函館を訪れた際に行きたいランチが食べられるお店|北海道
-

横浜デート・会食
横浜元町・山下公園を訪れた際に行きたい、中華以外のお店|神奈川