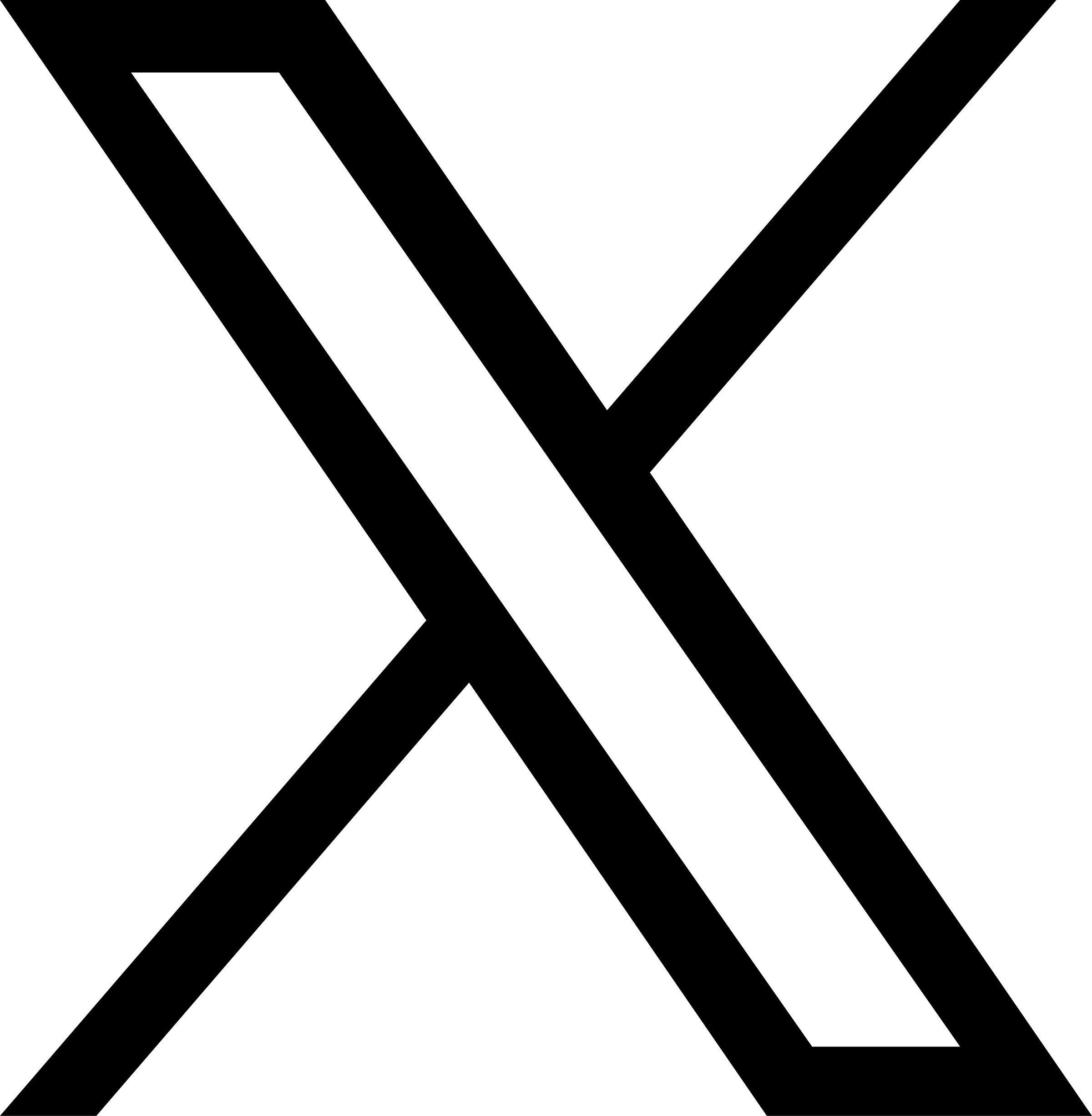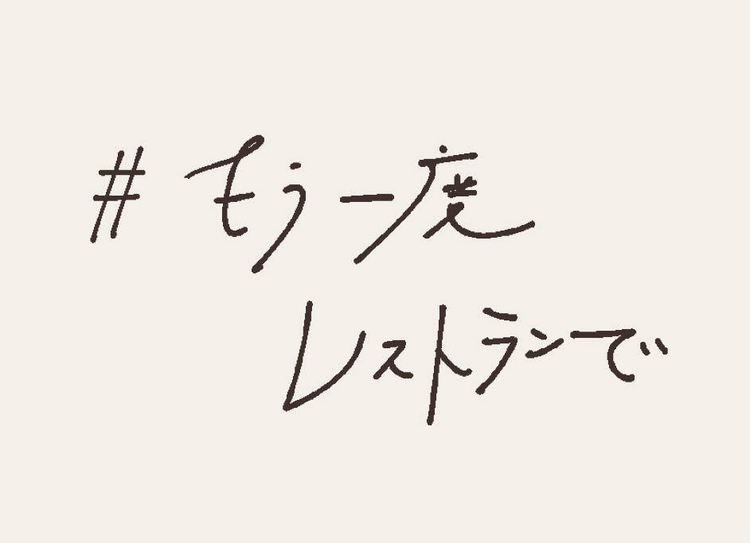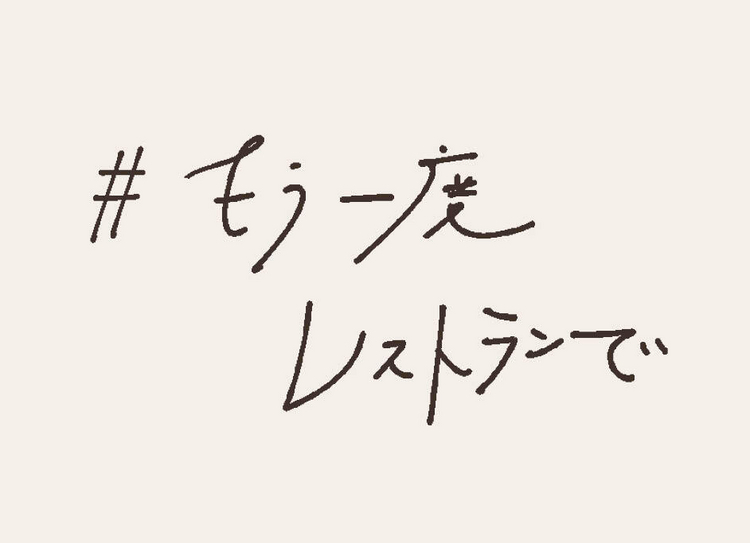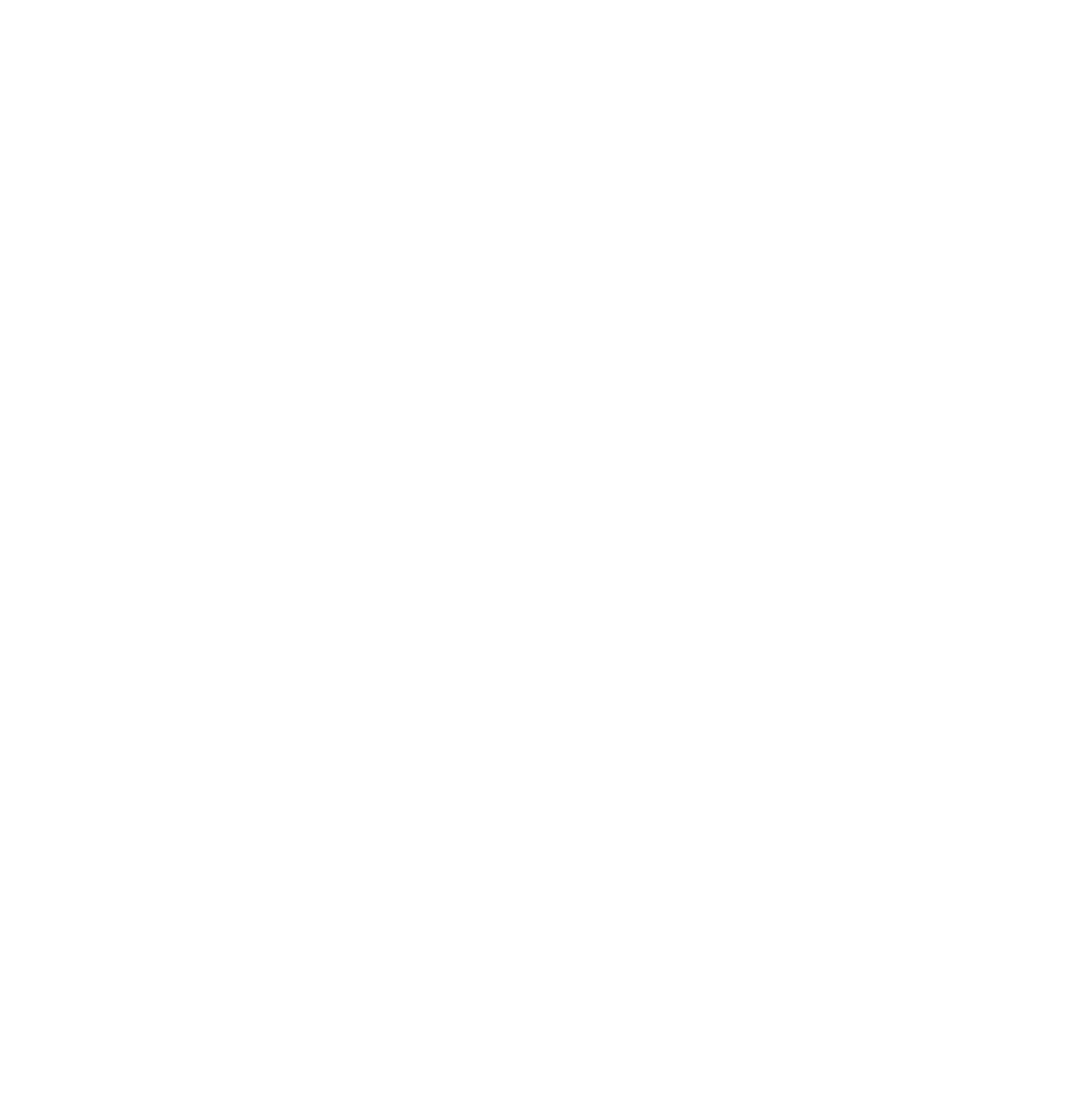<連載短編小説>#もう一度レストランで|「焼肉」宇垣美里
恋人未満の二人をあとおしし、家族の記念日をともに祝い、おいしいお酒に友だちと笑う。レストランでのありふれた光景が、特別なものだったと気づいたこの数年。レストランは食事をするだけの場所ではなく、人と人とが交わり、人生が動く場所だった。これは、どこにでもあるレストランで起こる、そんな物語のひとつ。

焼肉、それは祈り。どっぷりとタレに漬けられた肉の塊を網の上にそっと乗せ、わが子が如くじっくりじっくり育てた末に、ここぞというタイミングで食らいつく。食欲のままに、本能のままに。とって、やいて、くう。太古の昔から人類が生きるために踏んできたであろう工程をなぞれば、自分が人間という名の動物であることを、生きているってことを、実感できる。食べることは生きること。だから、私はまだ生きている。
「仕事、辞めたんだあ」
焼肉屋の個室に響いた園子の声は意図した通りののん気さで、そのがらんどうな明るさは我ながら耳障りでしかない。頭が空っぽな人間のフリをするのは特技の一つだったはずなのに、その嘘っぽさが情けなくて鼻の奥がギュっと切なくなった。え?、と真剣な眼差しで肉をつつきまわしていた藍が、撃たれたような勢いで顔をあげる。ふわりとはねた髪が耳周りのみにいれた明るいアッシュベージュの髪束を隠す。彼女がぱちくりと大きく瞬きすると、まぶたの上で濡れたように光る偏光パールが眩しくて、この子は綺麗になったな、と改めて思った。
大学の新入生ガイダンスで隣同士だった藍とは、もう十年以上の付き合いになる。彼氏ができた時、その彼氏にフラれた時、ゼミに受かった時、就活で祈られ続けた時……学生の頃、事あるごとに通っていた食べ放題の焼肉屋は、社会人になる頃には肉寿司を出してくるようなこじゃれたチェーン店に、三十近くなるとドライアイスの煙の中から肉が登場するようなしゃらくさい店へと変化した後に、実家みたいな雰囲気のこじんまりした店に落ち着いた。この店に来るのは三度目だ。私が希望する部署に配属が決まった時と、藍に彼氏ができた時、そして今日。
牛脂を塗り足らなかったのか、少し前に乗せたばかりの肉が網にぴったり張り付いてなかなか離れない。
「海外にでも行こっかな?ほら、カナダとか。」
めりめりと引きはがそうとした途端に端からぺりりと裂けた。ああもう、肉一つ上手に焼くことができない。沈黙は私の落ち度のようにしか思えなくて、どんどんと口が回る。
「まあ、私ぐらいビッグになるとさー 会社員には収らないよねー。」
回し車の中でどこかを目指して必死に駆けるハムスターの見る景色って、こんな感じなのかもしれない。盛り合わせで頼んだホルモンを言い訳するように次から次へと網へ乗せる。マルチョウ、ハツ、テッチャン、上ミノ、ツラミ。網に乗ったそばからじゅうじゅうと音をたて、あっという間に小さな網は肉でいっぱいになった。
私はこれからレールを外れる、それを知られるのが怖い。ふつうじゃなくなるのが怖い。
あんなに応援してもらったのに、あんなに頑張って入った会社だったのに。
ツラミ、が牛の顔の肉なのだと教えてくれたのは直属の上司だった。入社当初から面倒を見てもらい、育て可愛がってもらっていたその人を尊敬していた。なのに、園子がちょっとした賞を獲ったことは、彼の中で裏切り行為に当たったようだった。矢継ぎ早に飛んでくる怒鳴り声に委縮し、何をしても否定されることに疲弊し、丁寧なほど細かな嫌味に自尊心を削られた。ある朝、どうしても布団が重くて起き上がれなくて、もう全部やめることにした。
「まあこれも全部ネタになると思えばさー」
ははは、と笑おうとしたのに、浮き輪をつぶすときのような音が漏れる。全然思った通りの場所に口が動かない。さぞ情けない顔をしていることだろう。脂の爆ぜる音ばかりが響く。壁の奥から聞こえる若い男女の笑い声が、頭の中まで入ってきて柔らかな脳みそをめちゃくちゃに削り取る。逃げるんだ、ウケルー。
「もう笑わんでええんちゃうんかなあ」
そう口を開くと猛然とトングを構え、親の仇みたいに肉を網に押し付けてからひっくり返し、またひっくり返しする藍の目は燃えていた。穏やかな口調とは裏腹にぼろぼろと溢れ出す涙の粒に炭火が爆ぜる。
「全部笑って冗談みたいにコメディにして」
テッチャンの皮は少し焦げて油がぶくぶくと泡を立てている。
「それで楽になるんかなって思ってたから黙って笑ってきた。」
ミノやツラミから垂れたタレが焦げ広がり網を黒く浸食する。
「実際まあ笑えばなんとかなってたみたいやし」
ハツに入った格子模様の焼き目が美しい。
「でもそんなん全部まちがってたんやわ」
突如網から火柱が上がり、熱波が肌をさらう。藍はレモンサワーの中から氷を取り出し、ぽんと網の上に放った。
「怒るべきやってん」
ぐりぐりと網の上を踊らされ、炎を殺して瞬時に溶けていく氷から立ち上る、まっしろなけむり。
「何があんたから仕事を奪ったん?ゆるせへん」

全部笑って、笑ってもらって、どうにかネタにしてきたのに。それが大人のやり方だと思っていたのに。生き残るために薄ら笑いでごまかして見ないふりしていたそれは、心のどこかで腐り落ち、大きな穴を開けていた。
「もう!ホルモンっていつまで焼けばええん?」
泣きながら癇癪を起す藍の目元はアイラインが溶けだして、目の下に黒くに広がっている。はたと目の下に触れれば、私の目元もぐちゃぐちゃで、指先にマスカラとアイシャドウの残骸がべったり付いた。きったね。どんな顔してるんだ今?なんだか全部がおかしくなって、気づけば二人でケラケラと笑いだしていた。私が道半ばで転んだことを知ってくれている人がいる。傷ついて嫌になって逃げだした私の情けないその横顔を記憶していてくれる、そんな人さえいたら、それは独りじゃないってことだ。
「今日は私のおごりや、いっぱいたべや」
乱暴に目元をこすったせいで広がったラメをギラギラ光らせながら、藍が肉を皿に盛った。
タレのしっかり絡んだマルチョウは噛めば噛むほど肉の旨味がにじみ出る。ついで鼻を抜けるのは幸せが具現化した匂い。コリコリとしっかり弾力のある歯ごたえを堪能すれば、口いっぱいに広がった甘い脂がじんわりと体に染み込んで、どこかの細胞がふいに生き返るのを感じた。口の中に残った脂が勿体なくて、慌てて白飯をかっくらう。沁みる。肉は、やっぱり人を救う。
そういえば件の上司に中学生男子みたいな食い方だなと鼻で笑われたことを思い出した。それの何が悪いのだろう。凹まれ損なわれた心のどこかはまだ少し痛むけど、傷つけられた記憶は何度も自分を苛むけれど、補うように肉を口に運ぶ。その度に、藍がせっせと新しい肉を焼き、私の皿へ放り込む。育てるように、慈しむように。
私に優しいひとと食べるごはんは、美味しい。ひとまずは、それでいいと思えた。
著者プロフィール
-

-
宇垣美里 うがき・みさと
1991年4月16日生まれ 兵庫県出身。
2019年3月にTBSを退社、4月よりオスカープロモーションに所属。
現在はフリーアナウンサーとして、テレビ、ラジオ、雑誌、CM出演のほか、女優業や執筆活動も行うなど幅広く活躍中。

友達の実家みたいな雰囲気の中でいただく石鍋のお店。胡麻油の香りが食欲をそそります。お店の方が全部作ってくださるのでベストタイミングで食べられるのも最高。
【石頭楼アネックス】
-
電話:03-3470-4777
住所:港区六本木7-5-4
店舗詳細はこちら >
この記事を作った人
文/宇垣 美里 イラスト/yasuna 構成/宿坊 アカリ(ヒトサラ編集部) 企画/郡司しう
-

愛知県グルメラボ
名古屋市内でこだわりの肉料理が楽しめるオススメ店5選|愛知
-

北海道旅グルメ
北海道産の素材を使った料理が楽しめる店5選|北海道
-

河原町・木屋町・先斗町グルメラボ
人気の河原町エリア、鴨川近くにあるオススメのお店|京都
-

東京都デート・会食
記念日デートで訪れたい少し贅沢なお店5選|東京
-

新宿・代々木グルメラボ
新宿エリアで立ち寄りたい駅近のお店|東京
-

銀座食トレンド
【銀座焼肉 銀座サロンドエイジングビーフ】が移転リニューアル! “和の技法” × 熟成米沢牛の極上コースを体験|銀座
-

大阪府グルメラボ
お肉が食べたい! 大阪市内で和牛メニューを堪能できる店5選|大阪
-

三宮グルメラボ
神戸・三宮で仲間と盛り上がるならココ! 駅近のカジュアルなお店5選|兵庫
-

京都府デート・会食
京都デートに使いたい、雰囲気がいいお店5選|京都
-

神田・秋葉原・水道橋グルメラボ
神田・秋葉原エリアで、お酒と食事が楽しめるお店5選|東京