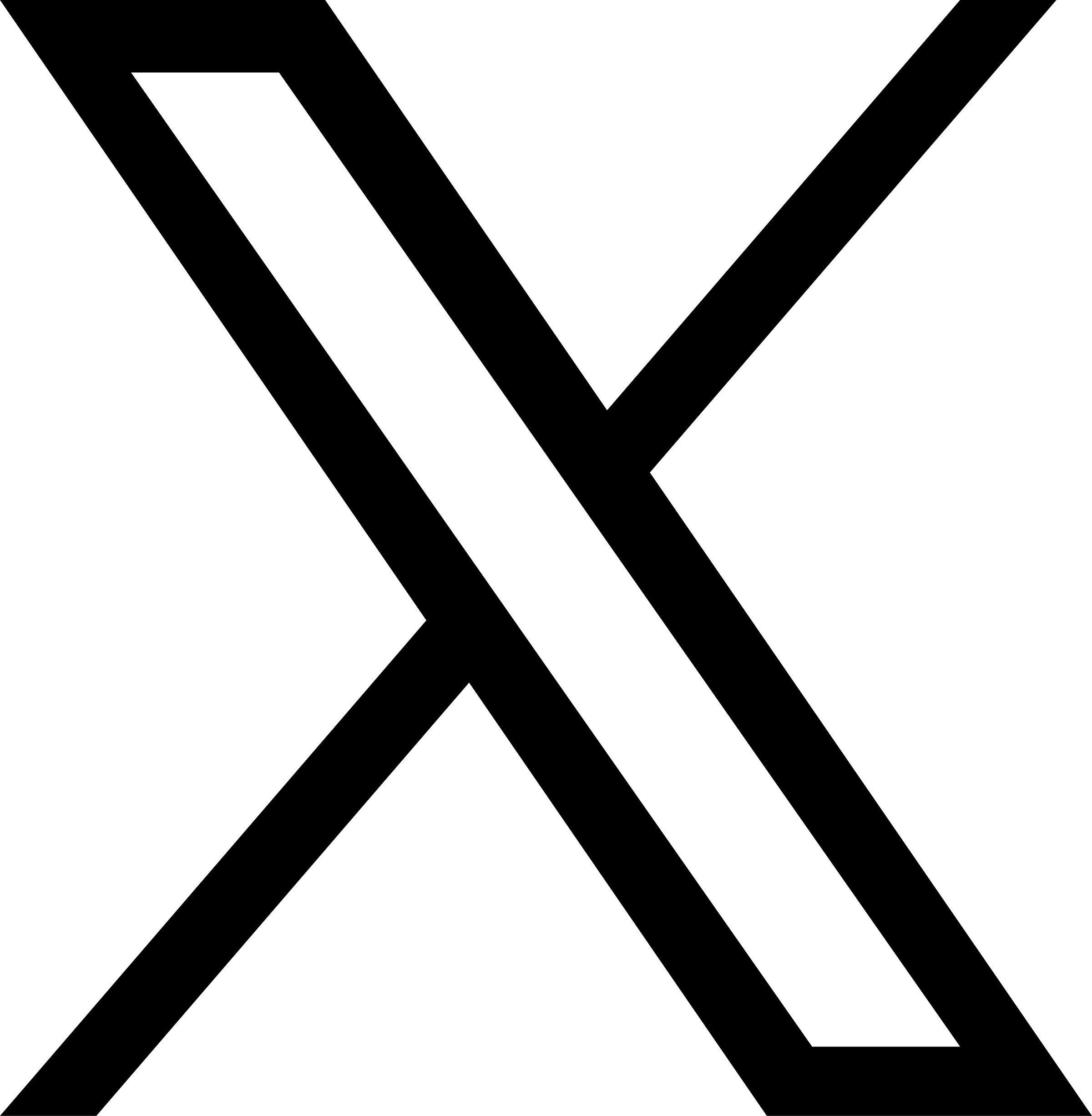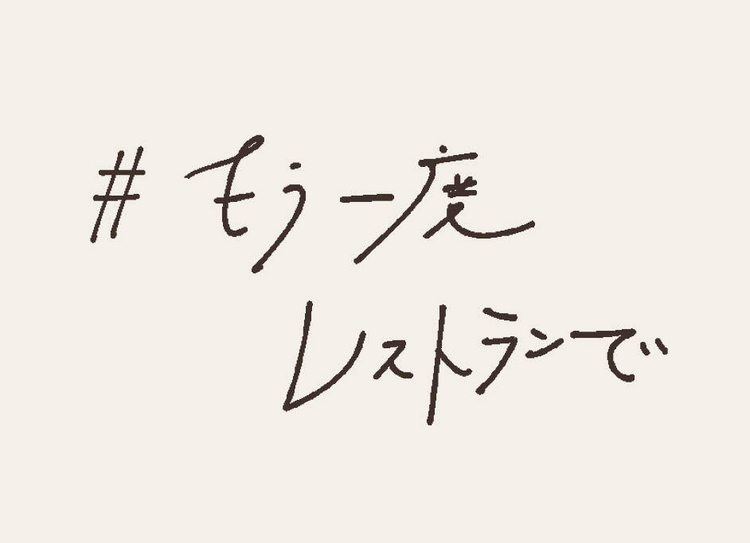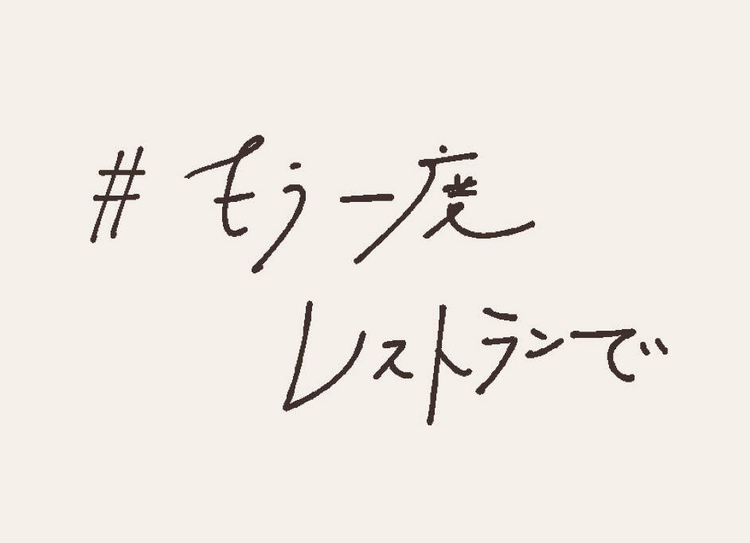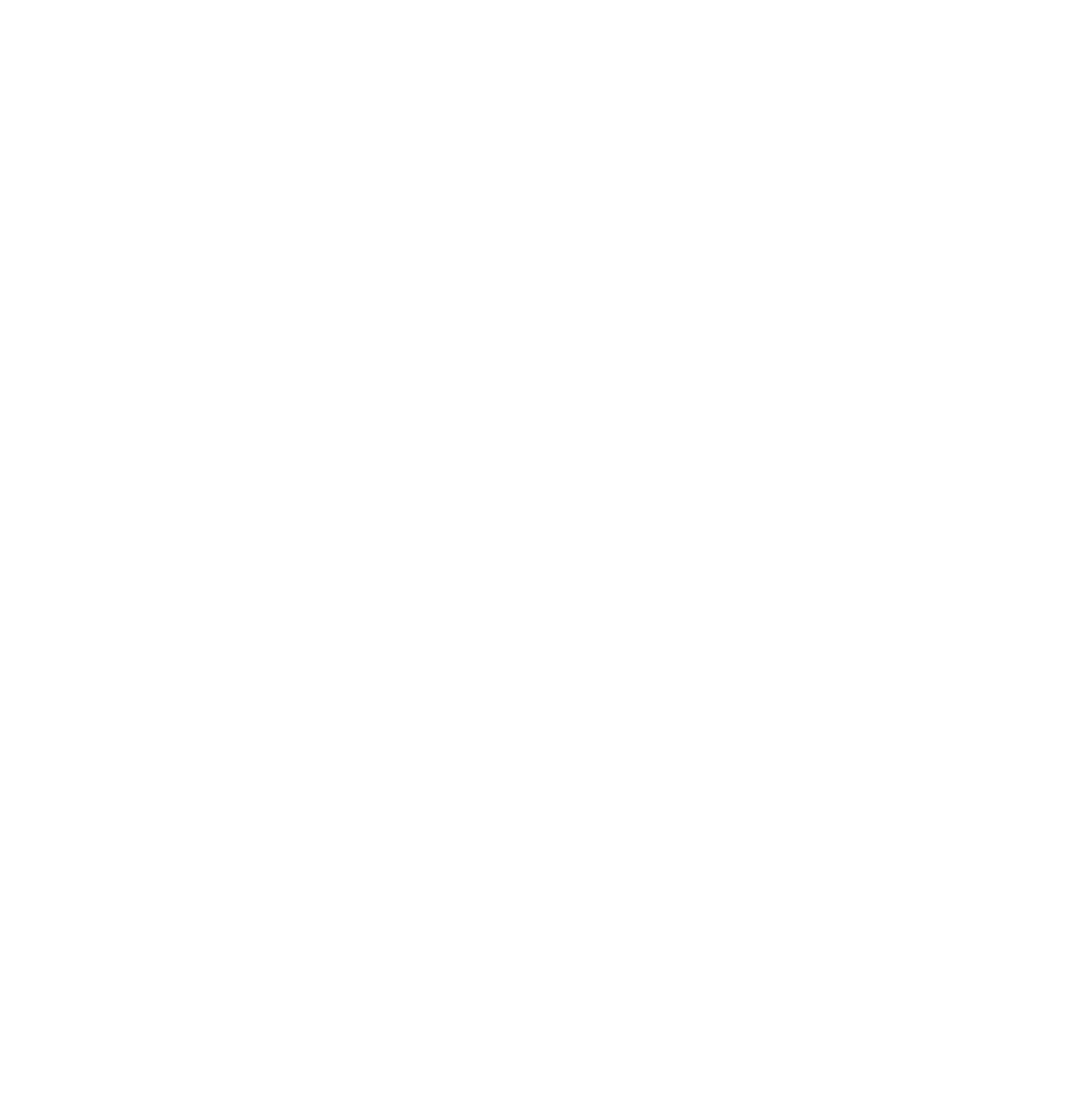<連載短編小説>#もう一度レストランで|「いわくとえにし」角田光代
恋人未満の二人をあとおしし、家族の記念日をともに祝い、おいしいお酒に友だちと笑う。レストランでのありふれた光景が、特別なものだったと気づいたこの数年。レストランは食事をするだけの場所ではなく、人と人とが交わり、人生が動く場所だった。これは、どこにでもあるレストランで起こる、そんな物語のひとつ。

そのレストランのことを、山中野乃実は心のなかで「いわく」と呼んでいる。勤めている広告代理店から最寄り駅の途中にある、古びた洋食屋で、昼はランチ、夜は酒も出すので食事というよりつまみとして、ロールキャベツやビーフシチュウやオムレツを頼む人が多い。もちろん店名は「いわく」なんかではない。洋食アポロというのがその店の名前だ。
この店のランチしか食べたことがなかった野乃実が、勇気を出してはじめてひとりで夜に訪れ、デカンタのワインと何品かの料理を食べたのは入社二年目で、これからはどんな店でもひとりで飲食できるはずだと自信をつけたのだが、翌日、仕事で大ぽかをして上司に叱責された。そのときはまだ、洋食アポロと自身の大ぽかに関連性を感じなかった野乃実だが、半年後、ふたたびひとりで夕食を食べたその翌日、当時交際していた恋人にふられた。
たまたまの偶然だろうけれど、なんとなく験が悪い気がしはじめた矢先、先輩社員が転職することになって、送別会を洋食アポロでやることになった。その二次会から帰る途中のどこかで野乃実は財布を落とした。そんなことはめったにないのに財布には八万円が入っていた。翌日の土曜日に冷蔵庫を買う予定だったのだ。財布は見つからなかった。八万円もたいへんな痛手だが、クレジットカードや定期券を再発行する手続きが地獄めぐりのようだった。
それからだ、野乃実が洋食アポロではなく「いわく」とその店を勝手に呼ぶようになったのは。とうぜんながら店自体に罪はなく、事情も秘密もないが、自分にとっていわくつきの店にしか思えなくなったのである。
地方で暮らす父親が余命宣告を受けて入院したと、母から電話で聞いたとき、野乃実はあえて「いわく」でひとりワインを飲み、蟹クリームコロッケとグリーンサラダとナポリタンを食べた。悪いことはもう起きた、もう「いわく」は終わった、だから「いわく」落としだ、これ以上悪いことは起きないはずだと、論理がまちがっている気もしたが、捨てばちのようにそう思い、料理をひとりで食べてワインを飲んだ。気分は最悪なのに料理はどれもおいしかった。父は、余命三ヶ月と言われたのに、一年後に亡くなった。七か月長く生きてくれたことと、「いわく」落としが効いたのかどうか、野乃実には判断できなかった。それからもうすでに、五年が経過している。
その日は、同僚の理歩に誘われて、「いわく」にいくことになった。ほかの店にしないかと提案してみたが、「あの店のポテトサラダがどうしても食べたい」と理歩はゆずらない。そう言われてみれば、たしかに野乃実にも「いわく」のおいしい一品一品が恋しく思い出される。
赤いタータンチェックのテーブルクロスに、カトラリーと、たたまれたナプキンののった皿がセットされている。座ってメニュウを広げ、好き好きに注文してから、テーブルの隅にスマートフォンがあることに野乃実は気づいた。こちらに向けてある画面が、ぴかりと光ったからだ。LINEで何か受信したらしい。反射的にのぞきこむと、「今どこ? もう着く?」と吹き出しが告げている。
「これ、忘れものみたい」と野乃実は理歩に言い、「お店の人に渡す?」と理歩はスマホをのぞきこむ。「私はもう着いたからカルディでなんか見てる」とまた吹き出しが告げ、漫画のキャラクターがきょろきょろしているスタンプが送られてくる。「本人がすぐに取りにくるんじゃない?」と野乃実が言い、「それもそうだね」と理歩はうなずき、ワインが運ばれてきて、二人は乾杯をする。
ポテトサラダや茸ソースのオムレツや小海老のフリットなどが次々と運ばれてきて、とりわけて食べながら、理歩は「毎日が単調すぎてうんざりしていて、転職を考えている」という、けっこうシリアスな話をはじめたものの、テーブルの隅のスマートフォンが気になって、野乃実は話に集中できない。ワインをボトル半分ほど飲んだあたりで、またスマートフォンの画面が光り、つい野乃実は見てしまう。「なんかあった?」「だいじょうぶ?」と続けて送られてくる。ああもう、何やってんの持ち主。野乃実はいらいらと背後のドアを振り向き、だれか入ってこないか見てしまう。
それからしばらく眠っていたようなスマートフォンはまた目を覚まし、「なんで無視?」と文字を浮かび上がらせる。野乃実は思わずそれに手をのばし、つい返信しそうになるが、
「ちょっと何やってるの、他人のスマホだよ」理歩に言われて我に返り、
「だってなんか……」と、ひとりごとのようにつぶやく。スマホの持ち主とLINEの送り主の関係もわからないのに、彼らのあいだにひびが入ってしまうと、泣きたいような気持ちになる。この店が、持ち主の「いわく」になってしまったらどうしよう。
あたらしいワインと湯気を上げるグラタンが運ばれてきたとき、野乃実の背後でドアが開く音がする。「あのー、すみません、さっきここでスマホを……」という声が聞こえるやいなや、野乃実はスマートフォンを握って勢いよく立ち上がっている。
「これ、これですよね、すぐ確認してください、光ってたから、すぐ連絡してください」と、ドアから半身を出している若い男性にスマートフォンを押しつける。礼を言って彼がドアの向こうに消えると、安堵のため息が漏れる。席に戻ると、野乃実のグラスにワインをつぎながら、
「ぜんぜん私の話聞いてなかったでしょ」と、理歩がにらむ。
「ごめんごめん、マジごめん」野乃実はすなおにあやまる。「なんかさ」ワインに口をつけて一口飲む。渋みがあって風味もあって、おいしかった。「ふつうに毎日がドラマチックだね」つい、思ったことを口に出す。「転職を考えてること自体、すでにもうドラマチックだよ」
この店で夕食を食べたから何かが起きたんじゃない、とはじめて野乃実は思う。私たちの日々は、何か起きることになっている。顔を上げられないくらいかなしいこと、飛び上がるくらいうれしいこと、何をしてもしなくても、そういうことは向こうからやってくる。今までもそうだったし、きっとこれかもそうに違いない。私たちにできることは、何かが起こらないようにすることではなくて、何か起きても、向こうから何がやってきても、へこたれないこと。ぺしゃんこにならないこと。なったとしても、またいつか、起き上がること。そう思っている自分に野乃実はびっくりする。はじめてひとりでここで食事をしてから、考えてみればもう十二年もたっている。
「もし仕事変わっても、ときどきこうしてごはんいっしょに食べてね」野乃実が言うと、
「なーんて、ずっと先まであんたと机並べてるかもだけど」理歩は笑って、グラスのワインを飲み干す。
あの人、名前も知らないあの若い人、LINEの相手に会えたかな。今日の失敗のことを、もう笑ってるかな。LINEの相手といつかここにごはんを食べにくるかな。そうしたら、この店はあの人にとって、いわくではなくてえにしだな。野乃実は酔いのまわりはじめた頭でふわふわと考えて、口元をほころばせる。

著者プロフィール
-

(撮影:垂見健吾)
-
角田光代 かくた・みつよ
作家 1967年生まれ 1990年「幸福な遊戯」でデビュー。
2005年「対岸の彼女」で直木賞受賞。
近著に「タラント」など。

このお店の料理は佐賀の食材をおもに使っているのですが、どの食材をどのように調理し、どのような酒と合わせたらもっともおいしく味わえるかを、考え抜いて提供してくれている気がします。私たちはただ、その料理と酒を、「おいしい」以外何も考えずに味わうだけでいい、という幸福なお店です。
【ゴブリン NISHIAZABU】
-
電話:03-5466-7728
住所:東京都港区西麻布2-13-19-2F
アクセス:乃木坂駅 徒歩9分店舗詳細はこちら >
この記事を作った人
文/角田 光代 イラスト/yasuna 構成/宿坊 アカリ(ヒトサラ編集部) 企画/郡司しう
-

海外旅グルメ 連載
ペルー・クスコ【MIL】(ミル)~ヒトサラ編集長の編集後記 第78回
-

海外旅グルメ 連載
ペルー【Central】(セントラル)【MIL】(ミル)~ヒトサラ編集長の編集後記 第77回
-

釜石/大船渡/陸前高田旅グルメ 連載
ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~vol.2|岩手・宮城 三陸の漁師町の魅力 その①
-

富山県連載
ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~vol.1|おいしい富山 その③
-

富山県旅グルメ 連載
ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~vol.1|おいしい富山 その②
-

富山県旅グルメ 連載
ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~vol.1|おいしい富山 その①
-

京都府グルメラボ
秋の京都でゆったり楽しむ、ちょっと穴場なお店5選|京都
-

横浜グルメラボ
横浜散策の途中で、サクッと立ち寄れる駅近のオススメ店5選|横浜
-

神奈川県デート・会食
三浦半島・葉山・鎌倉の海辺デートで立ち寄りたいお店5選|神奈川
-

麻布十番食トレンド
著名人が愛した名店「銀座キャンドル」の味を受け継ぐ洋食店。“大人の洋食店”が楽しめる麻布十番【TARO Azabujuban】
関連記事
-


2025.07.15食トレンド
国産うなぎ×いくらのご褒美“うな重“『国産うないくら重~あかね色の輝き~』|【薪焼うなぎ 銀座おのでら 本店】
-


2025.07.13旅グルメ グルメラボ
人気観光地の浅草でも安心! ヒトサラからネット予約が可能なランチのお店|東京
-

2025.07.12グルメラボ
渋谷・新宿エリアの駅近でランチを楽しめるモダンなホテルレストラン5選|東京
-

2025.07.11デート・会食
フランス料理の巨匠・三國清三氏監修のグランビストロ【Dining 33】で、夏限定のディナーコースを大満喫|麻布台ヒルズ
-

2025.07.10グルメラボ
ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【熱海 美虎】の『春の唐揚げ サクラエビの香り』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#12