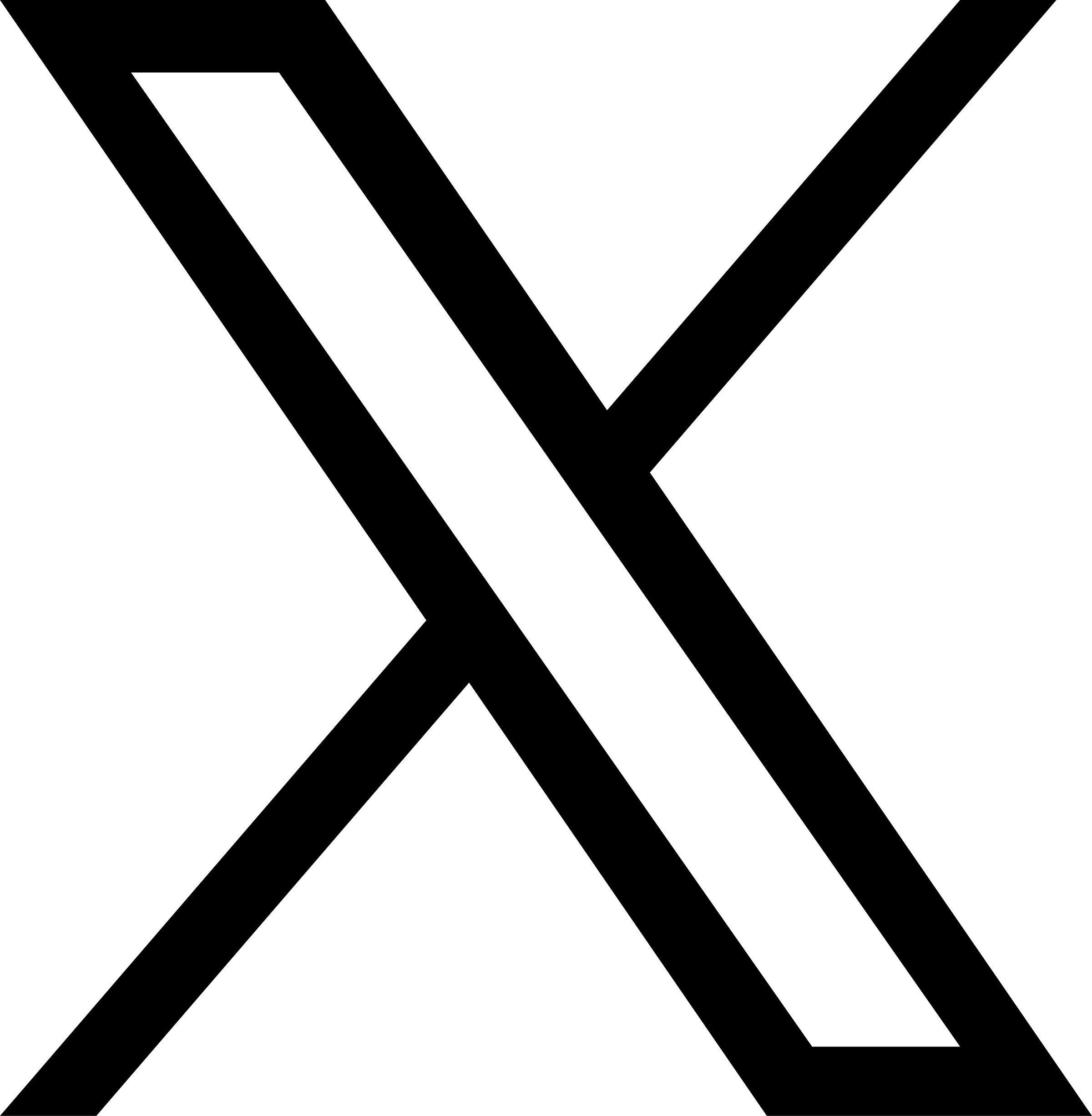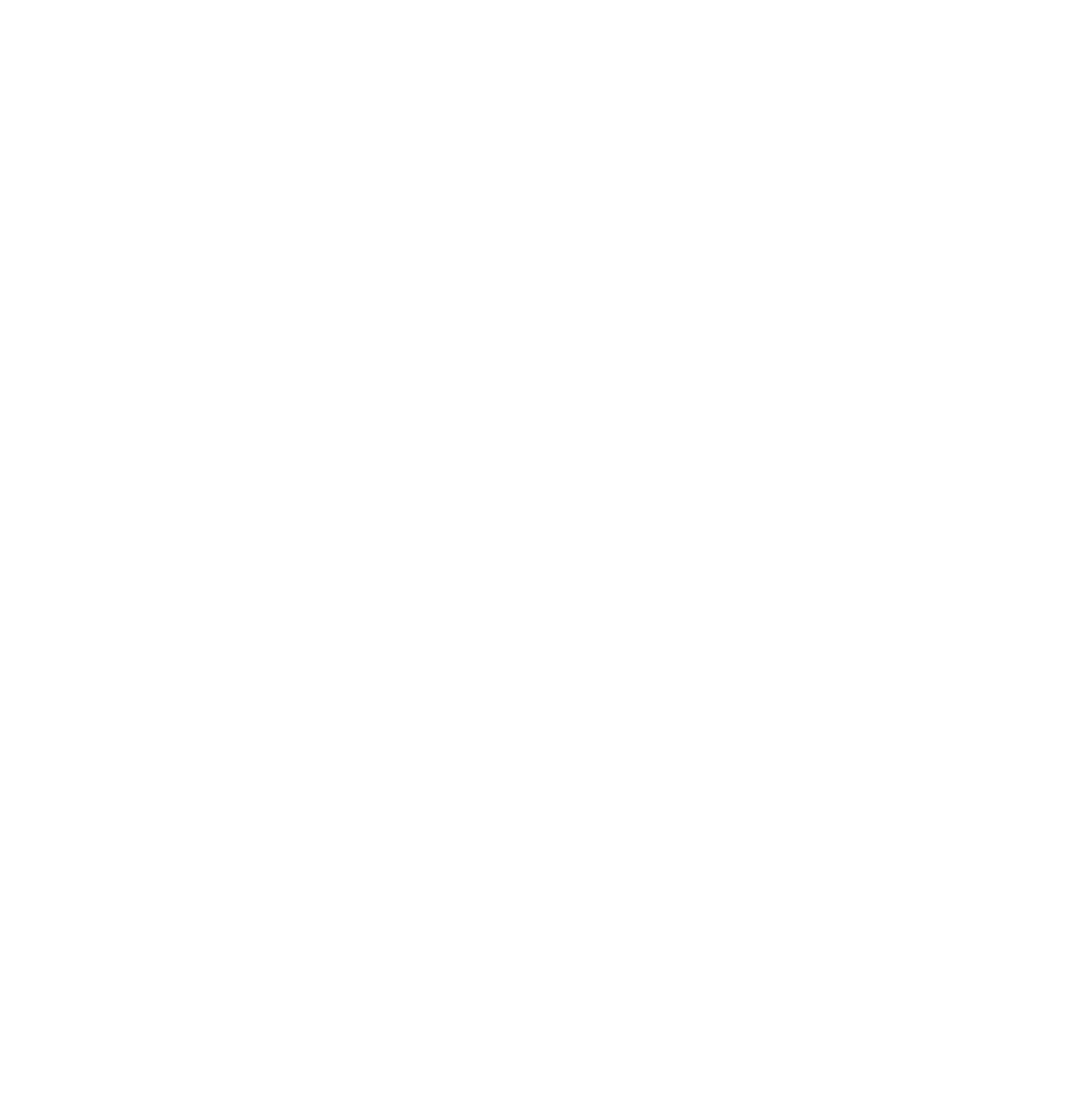埼玉・東川口に名店の予感。古民家と自家菜園、幼なじみコンビが織りなす【Restaurant KAM】
用事がなければまず降り立つことがないだろう埼玉県の東川口駅から徒歩圏内の住宅街に、2021年4月29日、実に興味深いレストランが誕生した。名は【Restaurant KAM】。腕を振るうのは、里山ガストロノミーとして注目を集めた【レストランビオス】出身の本岡将さんと、ローカルファーストを標榜して人気を博す【Maruta】出身の田代圭佑さんの幼なじみコンビ。その敷地内には本格的な自家菜園が設けられ、そこで採れた野菜や果実、ハーブを料理や飲み物に仕立てるのだという。なにやら名店の予感……。本能に突き動かされるままに現地を訪ねてみた。

JR武蔵野線と埼玉高速鉄道東川口駅から歩くこと約10分。今どきの一戸建てが立ち並ぶ住宅街の一角に一軒の日本家屋が佇んでいた。石塀にぐるりと囲まれたその様は屋敷風。ここだけ時計の針が止まっているかのような懐かしさに溢れている。門から中をのぞき込むと、窓辺には簾がかかり、庭先には昔ながらの日本家屋でおなじみの縁側が見えた。

築60年の古民家を利用した【Restaurant KAM】
飛び石を渡って建物に近づくと、左手には菜園。ちょうど盛夏の始まりで、様々な種類のトマトをはじめ、ナス、ピーマン、ズッキーニなどなど、驚くほどたくさんの野菜が実り、あたり一面に青々しさが漂っていた。懐かしい香りだ。子供の頃、田舎の祖父母の家を訪ねたときの記憶が蘇るよう。そんなことを想いながらぼんやりと玄関に佇んでいると、中から一人の男性が姿を現した。【Restaurant KAM】のシェフ、本岡将さんである。

【Restaurant KAM】のシェフ、本岡将さん。管理栄養士だった祖母の影響で料理が好きになったという
本岡さんと言えば、23歳の若さで静岡県を代表するフレンチレストラン「レストランビオス」の料理長に抜擢され、2018年には新時代の若き才能を発掘する料理コンペティション
「RED U-35」において最年少で準グランプリに輝いた実力派だ。なぜ、独立の地として東川口を選んだのだろう。東京で店をやろうとは思わなかったのだろうか。そんな素朴な質問を投げかけてみると、ご本人からはこんな答えが返ってきた。
「もともと静岡の里山にいたからか、東京で店をやろうという気はまるでありませんでした。それに独立するなら、【レストランビオス】のときのようにできるだけ自分で育てた野菜やハーブを料理に使いたいと思っていたのです。それで、造園業を営んでいた家族が所有するこの日本家屋を活用することにしました」

2021年4月29日の創業から数ヶ月しか経っていないが、庭の自家菜園はご覧の通りの充実ぶり
その自家菜園をつぶさに案内してもらうと、トマトだけでもさまざまな品種が食べ頃を迎えていた。優に7種類はあるだろうか。「これをお客様が来る直前に収穫し、もぎたてならではの野菜の力強さを味わっていただくお料理を提供しています」(本岡シェフ)。都会で暮らす者にとっては得難い贅沢。料理への期待がさらに高まった。

自家菜園で育てられた野菜たち。どれもこれもつやつやで、ヘタは針のように固い。まさしく生命力に溢れている
【Restaurant KAM】では玄関で靴を脱いで、中に上がり込む。誰かの家に招かれたような感覚で奥へ歩みを進めると、そこにはいかにも寛いで過ごせそうなダイニングが設けられていた。

お客様ひとりひとりに目が届くようにと、テーブルは2卓のみに絞られている
椅子を置いても圧迫された感じのない高い天井や、欄間に配された美しい組子細工、英国製のアンティークのテーブル。異質なものが違和感なく融合し、温かみのある雰囲気を演出している。そして、窓の外の緑あふれる菜園が目にやさしく、心をほどいてくれる。
肝心のお料理は、昼も夜も約7皿で構成されるコース1本のみ。一皿目には、例の「ゲストが来る直前に目の前の自家菜園から摘み取ったトマトで仕立てる」という前菜が運ばれてきた。

この日は、フルティカ、アイコ、プチプヨ、プヨマル、ロッソナポリタン、ゼブラトマトを使った一皿
いい香りだ。トマトの青々しさとアロマティカスの爽やかで甘い香りのハーモニーが心地よい。バニラヴィネガーのソースや、オレンジの皮の香りを移したエクストラバージンオリーブオイル、モッツァレラのクリームで味わいの変化も楽しめる。
「その日やって来る客を想像し、どうすれば一番喜んでもらえるかを考えるのが至福の時間なんです」と本岡シェフは語ったが、東京から訪ねた筆者にはドンピシャだった。
そして、お次は【レストランビオス】時代を知る人にとって懐かしい一皿であろう、本岡シェフのスペシャリテ「自家製リコッタ」の登場。

ガラス製のクロッシュを取ると、ヒッコリーの燻香がふわりと鼻をかすめる
上には薄いメレンゲ。中にはエクストラバージンオリーブオイル。聞けば、チーズの濃度は、夏はさっぱり、冬はこっくりと季節によってアレンジするとのこと。スモーキーな香りとミルキーな味わいの調和が見事であった。
アルコール派も驚くほど満足感のあるノンアルコールペアリングチーズとくればワインが予定調和だが、【Restaurant KAM】に来たらぜひノンアルコールペアリングを試してほしい。この日、二皿目の「自家製リコッタ」に合わせて供されたのは庭で採れた柑橘の皮を2日間かけて煮出し、黒胡椒とジュニパーベリーの香りを纏わせたドリンク。さっぱりと仕上げられたチーズとの相性は上々で、アルコール派の筆者にとっては新鮮な発見だった。
このノンアルコールドリンクを作り出すのは田代圭佑さん。ローカルファーストを標榜して食通に愛される一軒家レストラン【Maruta】出身で、本岡シェフとは幼なじみの間柄。聞けば、二十歳ぐらいの頃から「いつか二人で店をやろう」と話していたという。

【Restaurant KAM】のサービスを担当する田代圭佑さん
「せっかく自家菜園があるので、それを生かしてドリンクを提供できないだろうかと考えたとき、フルーツや野菜を発酵させてノンアルコールドリンクを作ることを思いつきました。スパイスや出汁、醤油を使うこともあります」(田代さん)。

田代さんが見せてくれた発酵ドリンクの一例。左からみかん×山ふじ、ヤマモモ、グリーンキウイ×山の花
既成概念にとらわれず、自由な発想で素材が組み合わされたものもあり、新鮮な驚きにふれている。かと言って、奇を衒っているようには感じられない。どれもこれも料理にきちんと寄り添ったものばかりだ。それはプロフェッショナルの仕事であると同時に、互いの繊細な感性を熟知した幼なじみコンビだからこそ実現できることなのかもしれない。

畑で採れた野菜のサラダにはハイビスカスを使ったドリンクをペアリング。この後、料理は魚料理、肉料理、デセール、ミニャルディーズと続く
なお、【Restaurant KAM】のKAMとは、それぞれの名前のKeisukeとMasashiの頭文字をAndで繋いだもの。2人の目が届く範囲でできることを着実にこなしてお客様に満足してもらいたいからと、1日のゲストは最大8名程度。予約は電話のみで受けている。

息がぴったり合った1993年生まれの幼なじみコンビ、田代圭佑さん(左)と本岡将さん(右)
「どんな店に育てていきたいか?」という問いかけに対して本岡シェフはこう言った。
「先のことはあまり考えません。とにかく目の前にあるひとつひとつの出会いを大切にすること。そのためにはけして欲張らず、身の丈を知ってお客様に向き合うことだと思います」。
【Restaurant KAM】で実践されているのは極めてシンプルなことだ。つまり、自分たちが丹精込めて育てた食材を、食べる人が喜ぶようにと思案しながら料理に仕立てるのは、かつては誰もが当たり前のように行っていたことだが、今やそれが難しくなり、複雑になっている。高い理想論を掲げるのではなく、地に足を付け、足元を固めて進んでいこうとする二人は、とても爽やかで清々しい。帰路につきながらやさしい気持ちに包まれたのはだからなのだと合点がいった。

【RESTAURANT KAM】
-
電話:080-4623-0829
住所:埼玉県川口市戸塚3-1-13
アクセス:東川口駅 徒歩8分店舗詳細はこちら >
この記事を作った人
撮影/佐藤顕子 取材・文/甘利美緒
-

秋田県連載
ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~秋田③
-

秋田県連載
ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~vol.4|秋田①
-

全国グルメラボ
香味野菜が決め手【ピアット スズキ】の『ポルペッティ』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#9
-

全国グルメラボ
ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【Nabeno-Ism】の『大ぶりレタスのシーザーサラダ』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#8
-

東京都デート・会食
大切な記念日に訪れたいワンランク上の店|東京
-

大阪府デート・会食
大阪の接待・会食にオススメしたい個室があるレストラン |大阪
-

福岡県デート・会食
福岡の接待・会食にオススメしたい個室があるレストラン |福岡
-

山口県旅グルメ
NYタイムズ紙選出「2024年に行くべき52か所」に選ばれた山口に行った際に訪れたいお店|山口
-

銀座デート・会食
おもてなしや接待・会食に使える銀座エリアのお店 |東京
-

東京都デート・会食
出会いと別れの春に最適! 歓送迎会でオススメしたい東京のお店 |東京
関連記事
-


2025.07.13旅グルメ グルメラボ
人気観光地の浅草でも安心! ヒトサラからネット予約が可能なランチのお店|東京
-


2025.07.12グルメラボ
渋谷・新宿エリアの駅近でランチを楽しめるモダンなホテルレストラン5選|東京
-

2025.07.11デート・会食
フランス料理の巨匠・三國清三氏監修のグランビストロ【Dining 33】で、夏限定のディナーコースを大満喫|麻布台ヒルズ
-

2025.07.10グルメラボ
ひと手間加えるだけで一段とおいしくなる【熱海 美虎】の『春の唐揚げ サクラエビの香り』のつくり方|「一流シェフのヒトサラレシピ」#12
-

2025.07.09食トレンド
屋形船【鮨 おりがみ】開業|ミシュラン一つ星店監修、“8席限定”の東京湾船上鮨体験