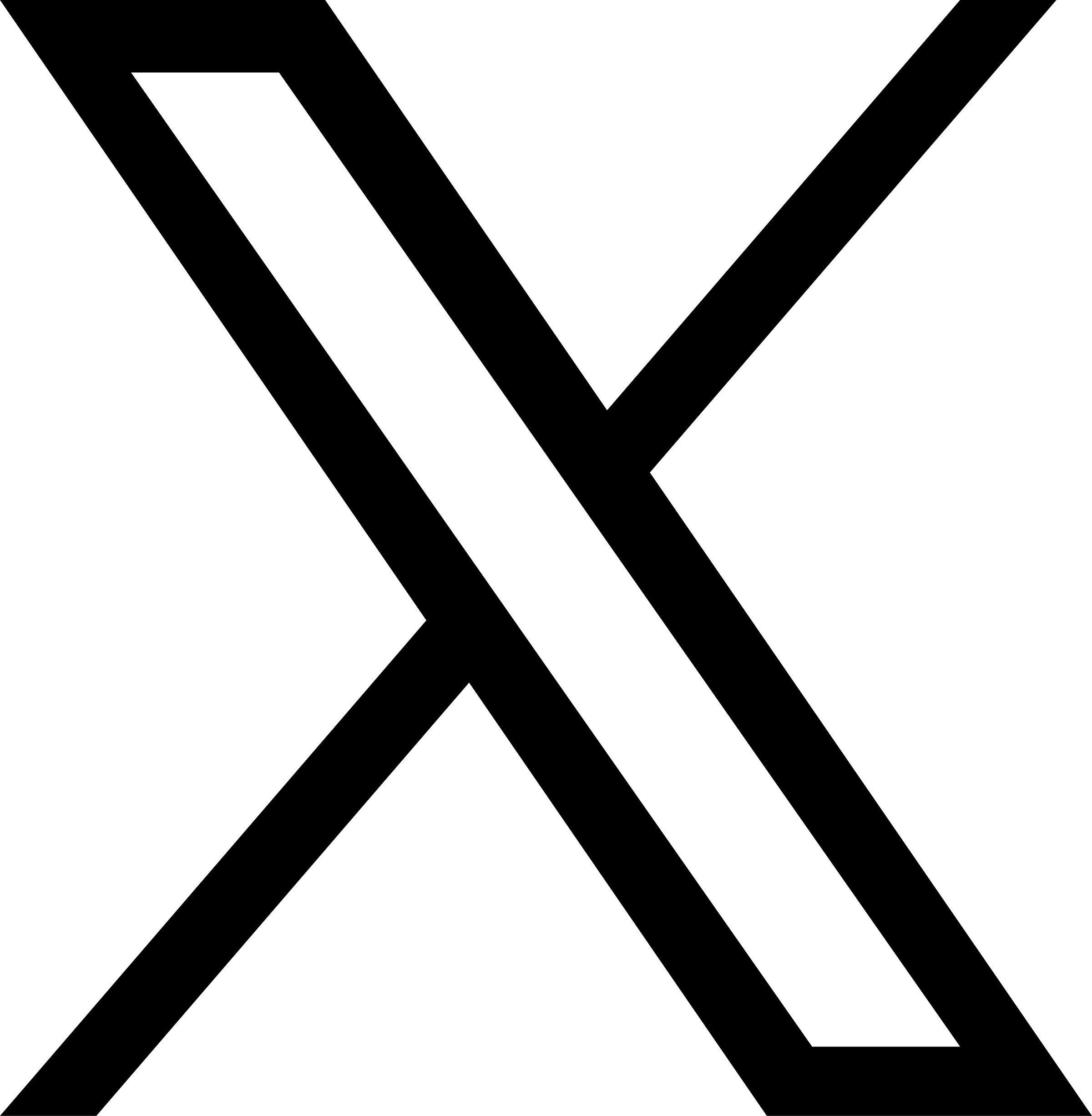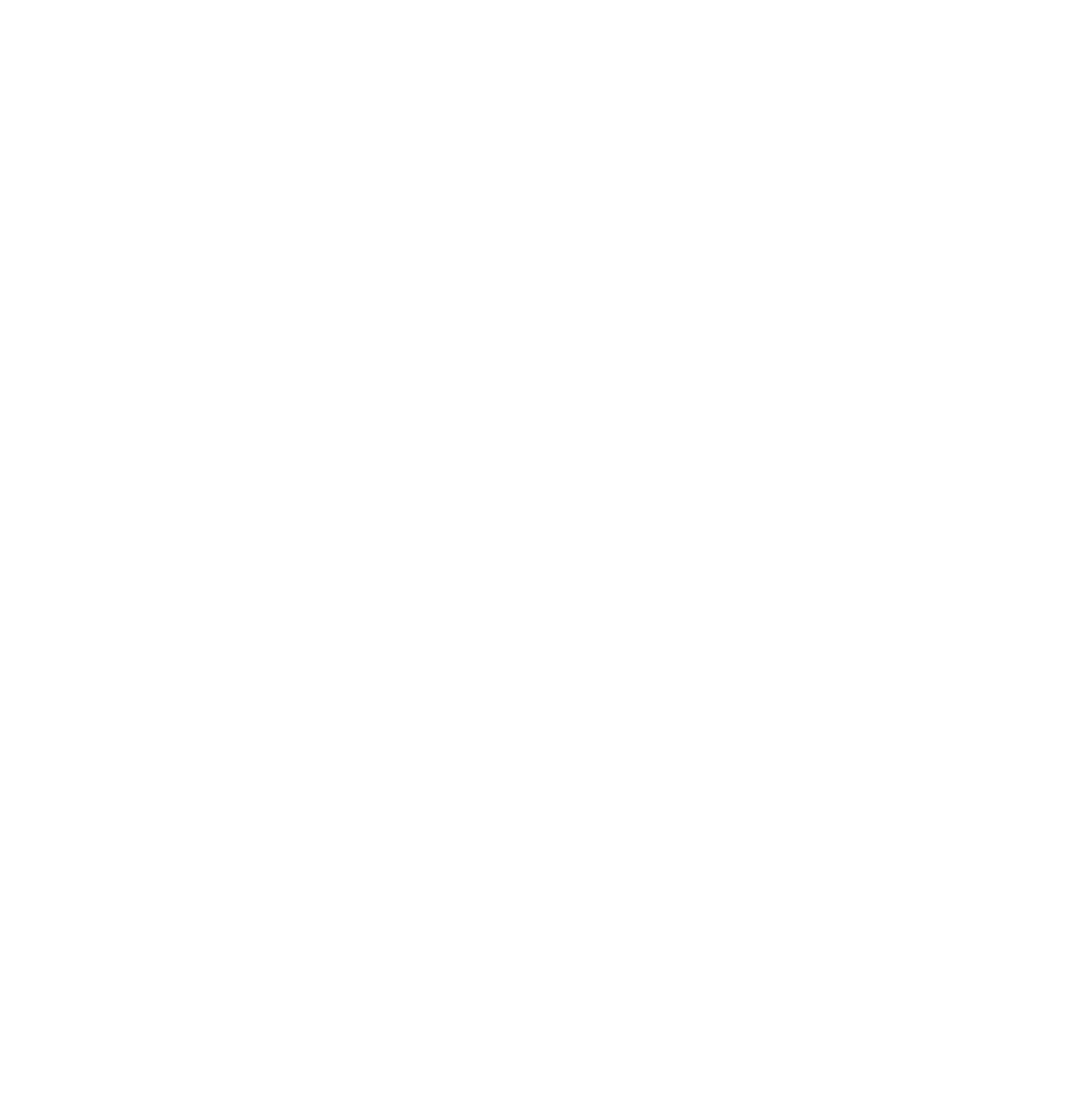一串に宿る美意識。東京・麻布十番【酉囃子】で焼鳥の新境地に出合う
焼鳥の常識を覆す一串に出合える、東京・麻布十番の人気店【酉囃子】。炭火と薪火を駆使して鶏の旨みを極限まで引き出したコース料理は、多くの人を魅了している。繊細な技と美意識が光る、新時代の焼鳥を体感してみてほしい。

歴史を辿れば、遥か平安時代にまで遡ると言われる焼鳥。江戸時代には、現在の原型とも言えそうな串に刺すスタイルが生まれていたようだが、「鳥」といっても鶏ではなく、鴨や雉、雁といった野鳥の類が中心だった。
やがて肉食が解禁された明治期になると、鶏の内臓などを焼いて提供する屋台も現れ、大正12年の関東大震災以降から昭和にかけては、東京を中心に焼鳥の屋台がぐっと広まっていく。そして、戦後。ブロイラーの普及とともに、焼鳥は大衆料理としての市民権を得ることになる――。
このように、時代とともに変遷を重ねてきた焼鳥シーン。それが今また、令和を迎え、著しく進化してきている。

紀州備長炭に加えて、ここでは薪も導入。素材の特質に合わせて焼き分けている。焼きの丁寧さも、林さんならでは
かつて、昭和の時代。コースでいただく高級焼鳥店といえば、老舗の京橋【伊勢廣】か、麻布十番の【門扇】くらいのものだった。それが今では、どうだろう。一斉スタートのおまかせスタイルが焼鳥店でもすっかり定着し、多くのフーディらの舌を捉えている。中には“鳥割烹”と呼ぶ方がふさわしい店もあり、ようやく焼鳥も、鮨や天ぷらと肩を並べる日本料理の一つとして、その認知度を高めつつあるようだ。

エレベーターを降りると、目に入る木の表札。焼鳥業界をより一層盛り立てたいとの思いから、囃子の名をつけたとか
そんな状況下、2025年の2月、彗星の如く現れた焼鳥店が、ここ【酉囃子】だ。麻布十番のビルの3階。扉を開ければ、コンパクトながら静謐な和の空間が出迎えてくれる。焼鳥店と聞いていなければ、鮨屋か割烹店と見まごうほど。凛として趣のある雰囲気に、自ずと期待は高まってくる。

カウンター8席のみと小体な空間ながら、静謐な趣はさながら割烹か高級鮨店のよう。凛とした空気が漂う
ご主人の林裕太さんが、同店の前身である神楽坂【焼鳥茜】をオープンさせたのは遡ること9年前。33歳の時のことだ。既に予約困難な人気店であったにも関わらず、暖簾を一旦おろし、10年目を迎える節目のこの年にリスタート。更なるステップアップを目指して店名も変え、新天地へと挑んだ林さん。新店では、炭火に加えて薪火にもチャレンジ。そこには、“焼鳥”を一つの料理として完成させ、世界に羽ばたかせたい。より多くの人たちに自分の焼く焼鳥を味わって貰いたいとの切なる想いが秘められている。

コースの最初に出される烏骨鶏の卵の茶碗蒸し。ふるふるとした滑らかな食感が胃に優しく、食欲を促してくれる
その静かな信念は、コースを彩る一串一串を味わえば、一目瞭然だ。席に着くと、最初に出されたのは『烏骨鶏の卵の茶碗蒸し』だった。
具は一切なく、表面にうっすらと生姜風味の薄葛餡が敷かれているのみの潔さ。これがいい。やわやわと仕上げた卵生地の滑らかさと、だしの旨みが混然一体となって舌にじんわりと伝わってくる。余計なものは一切加えず、素材の本質を伝えたいと考える林さんの料理観が、この一品からも汲み取れるようだ。
焼きたての『枝豆』が出たあと、供されたのは、比内地鶏とほろほろ鳥の『2種の胸肉の塊り焼き』。中心をわずかにレアに残した肉片は、しっとりとして鶏本来の静かな旨みが味蕾に染みる。これから始まる焼鳥への序奏にふさわしい味わいだ。

焼鳥の串は『ねぎま』からスタート。写真は、秋田高原比内地鶏の雌の胸肉。黄金色の美しい焼き色が、そのおいしさを物語っている。
そして、いよいよ焼鳥の串がスタート。口開けは、比内地鶏の『ねぎま』。焼鳥のごく定番的な一本だが、ここではもも肉ではなく胸肉を使用。黄金色の焼き色も美しい一串をよく見れば、胸肉が皮で丁寧に巻かれている。皮付きのままカットした肉をただ刺すのではなく、皮を一度胸肉から剥がし、カットしてから一つ一つ巻いているのだ。
というのも、火の入るスピードの異なるねぎと胸肉が、同時に焼き上がるようにとの配慮から。ねぎ自体も幾分細めにしているが、胸肉を皮できちんと覆うことで、肉への火の入りが、ある意味“間接的”になり、焼きすぎを防げるうえ、皮の脂が肉にまわり、パサつくことなく、ふくよかに焼きあがるという寸法だ。
アツアツにかぶりつけば、サクッとクリスピーな皮と、しっとりと柔らかな身の合間から、肉汁が口中に滴り落ちる。焼鳥としての勢いはありつつも、丹念な焼きの見事さ、美しさが、料理としての品格を漂わせている。

秋田比内地鶏の手羽。食べやすいよう骨を抜き、青柚子を忍ばせている。比内地鶏は、バランスの取れた味わいが魅力
次の『手羽』も、林流の一手間がかけられている。手羽の骨を抜き、そこに青柚子を忍ばせているのだ。手羽の濃密な脂の旨みが口中を覆いつつも、柑橘の風味が後口をすっきりとまとめ、続く一串へとつないでくれる。塩加減も絶妙だ。
続いて、「茜」時代からの定番メニュー『自家製さつま揚げ』が登場。クミンとチーズが入った人気の味だ。揚げたてに頬を緩ませた後、皮ごと焼いた『蕪』が、その葉とともに運ばれてきた。瑞々しさを残した蕪が、脂にやや疲れ気味の舌を優しくリセットしてくれる。何気ない焼き野菜に見えて、その実、根菜を丸焦げにすることなく潤いを残すよう直火で焼くのは難しい。
「蕪などの野菜類は、ゆっくり火が入る薪の熾火を使っています」とは林さん。
薪火は、野菜のほかに鶏肉にも使用。パリッとさせたい皮は炭火で焼き、一方で身の部分は薪の熾火でジューシーさを残すように焼き上げるなど、鶏の各部位の特性を見定めて適材適所。炭と薪とを巧みに使い分けている。

ほろほろ鳥の『レバー』。強火で焼きながらも、タレに何度も繰り返しつけながら焼くことで、レアな食感を生み出している
さらに、『レバー』には藁を使って薫香をプラス。とろけるような舌触りと甘みに、スモーキーな香りがキリッとしたアクセントを添え、何本でも食べられそうだ。こうした熱源の使い分けも、より完璧な焼鳥を追い求める林さんらしさが表れている。
もちろん、熱源だけではない。鶏そのものへの探究心も実に旺盛だ。
「茜」時代からの高原比内地鶏とあいち鴨に加え、現在は滋賀の淡海地鶏や名古屋コーチン、鹿児島の黒さつま鶏の黒王、茨城のほろほろ鳥など、良いと思った鶏は積極的に試しているとか。現在は、その中から毎日2〜3種を選び、部位によって使い分けているそうで、2種の鶏の食べ比べを楽しめるなど、焼鳥ラバーにとっては垂涎のコース内容となっている。

〆の『煮麺』。鶏ガラスープと鶏節でとっただしを合わせ、鶏挽肉でクラリフェしたコンソメに、極細の素麺がよく合う
ちなみにコースは13,000円(2025年6月取材時)。一品料理や串もの、締めにデザートまで、約20品近くが供される。その締めには『煮麺』と『親子丼』の2種を用意。中でも、絹糸のように細くしなやかな素麺に、クリアな鶏のコンソメがバランスよく絡む『煮麺』は、林さんの自信作だ。鶏節と鶏ガラを12時間火にかけてじっくりと旨みを引き出したスープに、さらに鶏挽肉を加えて澄ませたコンソメは、それ一品でも充分に満足できる佳品。有終の美を飾るにふさわしいおいしさだ。

ワインを愛する林さんだけに、シャンパーニュとブルゴーニュが中心の品揃えは充実。グラスワインは1,800円〜
一手間かけた焼鳥串の数々で攻めながら、季節の野菜や一品料理で緩急をつけ、シンプルな茶碗蒸しに始まり、クリアなスープ麺で終わる――その構成も見事だ。
遊び心がありつつも、やりすぎない程合いの良さ。新時代のあるべき焼鳥店の一つの形が、ここにある。
この記事を作った人
撮影/佐藤顕子 取材・文/森脇慶子
-

京都駅旅グルメ
京都駅の目の前! 京都タワーサンドでしっかり食事がしたいときにオススメのお店
-

東京都グルメラボ
至福のミルキー体験!東京で旬の牡蠣を堪能できるレストラン|銀座・麻布などの名店
-

淀屋橋・本町・北浜グルメラボ
本町オフィス街のオススメグルメ|大阪
-

岡山県グルメラボ
岡山・倉敷で人気! 一人ランチから飲み会まで、気軽に入れる地元民おすすめの普段使いの名店
-

福岡県グルメラボ
福岡市内で美味しい肉・野菜を堪能。食材へのこだわりが光る至福のレストランまとめ
-

博多グルメラボ
2026新年会|博多で人気の居酒屋5選!個室や飲み放題、大人が選ぶ外さない名店
-

表参道・原宿・青山食トレンド
表参道・青山に大聖堂を望むラウンジ&ダイニング、結婚式場レストラン【St.GRACE Lounge & Dining】オープン
-

博多旅グルメ
博多・中洲は「カウンター」が正解! ひとり飲みや出張でも楽めるおすすめのお店
-

愛知県グルメラボ
元気を出したい時に。スタミナ補充にはとっておきの肉料理を! 名古屋コーチンはじめ、牛肉、豚肉を楽しめるお店|愛知・名古屋
-

人形町・門前仲町・葛西食トレンド
予約困難店【渡邊料理店】に姉妹店が誕生! 多彩なアプローチで全皿に薪火を取り入れたフランス料理|門前仲町【jiü 慈雨】