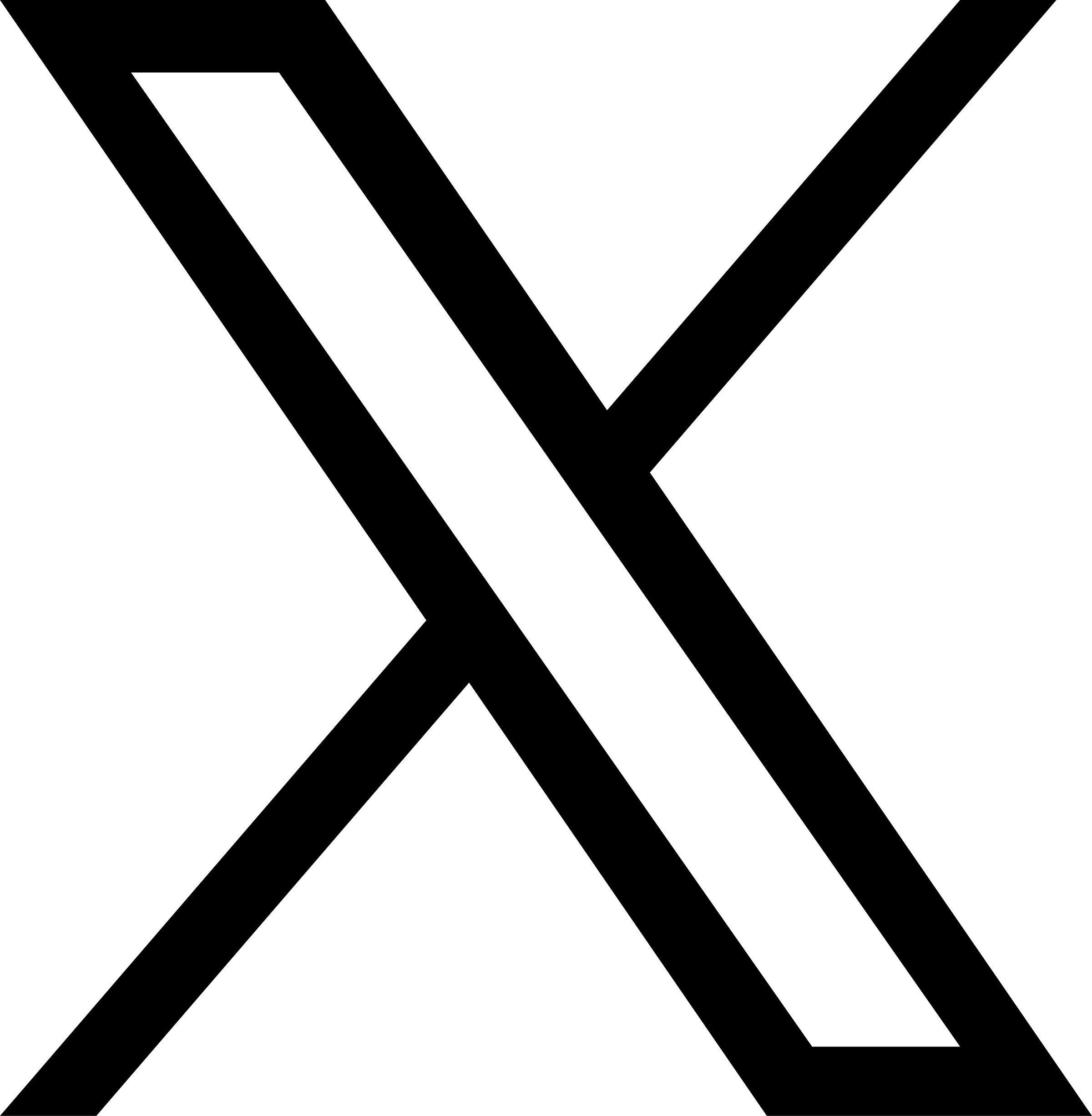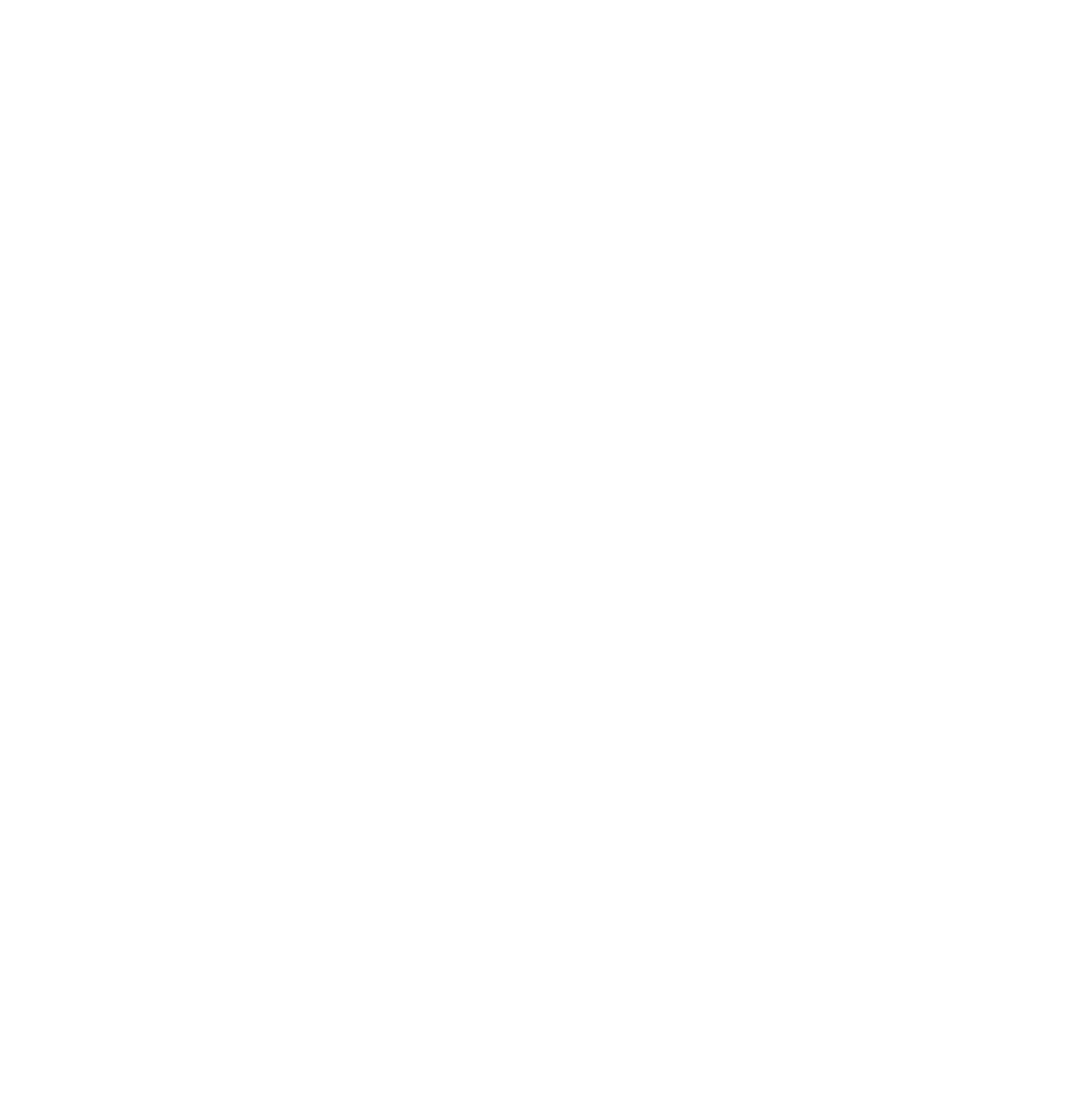一滴入魂のだしと炭火の香りに酔いしれる気鋭の日本料理店【炎水】東京・中目黒|ニュースな新店
食材の魅力を引き出す炭火の炎と、馥郁たるだしの香り。そんな和食の真髄に向きあう決意を名前に込めた日本料理の店が、2020年12月中目黒にひっそりとオープンした。店主は【日本料理 龍吟】で副料理長をつとめていた伊藤龍亮さん。研ぎ澄まされた美味の世界に魅了される人々で、すぐに予約困難店になりそうな予感だ。

「一瞬の香りやおいしさを捉えて、時差なくゲストに届けたい」
最初の一皿、『さといもと白粥』のシンプルで滋味深い味に、きっとこの店を好きになると予感はしていた。その予感が確信に変わる瞬間は、お椀物が出る直前にやってきた。
「どうぞ、まずこちらを飲んでみてください」。
手元の小さな盃に湛えられた黄金色の液体は、今目の前でとったばかりのだしだ。口元に近づけると、ふわりと優しい鰹節の香りが鼻をくすぐる。
口に含めば、鰹の香りに混じって、昆布の旨みと自然の塩み、そして水の甘みがまろやかに融合し、完璧に調和している。調味もなにもしてない無垢なだしは、もうこれ以上ないくらいの澄んだ味わいで、追いかけてくる深みが体にじんわりと染み込んでいく。
鰹と昆布だけなのに、なんておいしいんだろう。

カウンターの目の前で取る、一番だし
だしのおいしさがひときわ身にしみるのは、日本人のDNAからだろうか。それにしても、こうした素材の魅力を組み合わせて生まれる"奇跡のような"味に出合うたび、最初に考えた昔の人々は、どうやってこの作り方にたどりついたのだろうと思いをはせてしまう。
けれど、そんな先人たちが見つけた美味の方程式を、もっとおいしく、洗練させていくのは、続く現代に生きる料理人たちだ。先人からの知恵を自分なりに突き詰め、磨き、自分たちの味にして、どんどん料理は進化していく。

店主の伊藤龍亮さん、38才。ソムリエの資格も持つ
【炎水】の店主、伊藤龍亮さんは【日本料理 龍吟】で9年半働き独立。最初はサービスを2年、次の4年を煮方、3年を炭焼き場と要のポジションを任され、副料理長として同店を支えてきた。師匠の山本征治さんからは、自分の目の前にあるものではなく、例えば椀ものなら、ゲストがふたを開けた時に感じる香り、味わいをどう感じて欲しいか、完成形を考えて料理をすることを徹底的に教え込まれた。
自分の店を出すと決めたとき、毎日、だしをとる日々のなかで、ゲストがおいしいと感じる究極の椀物について、ずっと思いを巡らせたという。
まず、削りたての鰹節のいい香りを伝えたいから、一組ごとに鰹節を手削りにしてだしをとろう。そして鰹節の香りは欲しいけれど、鰹節が勝つのではなく、昆布のまろやかな旨みを出したい。それには、鰹節の削る幅を広く、長くすれば、温めた昆布だしと合わせるときに、一気に香りをうつし、適度な旨みを残し、理想的なだしが取れるかもしれない……。
そうして日々、試行錯誤しながら納得のいくだしを模索していった。

削られたばかりの鰹節。一片が長く、艶がある。「薄すぎても厚すぎてもダメなんです。削るというより、適度に薄く均一に切るイメージですね」と伊藤さん
そこで、こだわったのが、鰹節を削る道具だ。
既製のもので納得のいくものは一つもない。探しに探し、薄く削れるカンナを作る大工道具の職人と巡り会う。そして、ようやく思い通りの鰹節カンナをつくってもらうことができた。
使う鰹節は、指宿にある酒井商店のもの。カビつけをし、5回天日干しをした本枯れ節。保管にも気を使い、わずかな水分が中に残っている状態で削る。一組ごとに目の前で見事にリボン状に削り上げられた鰹節は艶があり、薄いのにへたらない。そんな理想の鰹節に合わせるのは、品がいいが旨みもしっかり出る奥井海生堂の蔵囲の利尻昆布。さらに水は、その旨みを出すために、超軟水の鹿児島の垂水の水を取り寄せている。
温めた昆布だしに鰹節を加えると、いい香りがカウンター全体を包む。それを、ほんのひと息置き、こし器を使わずそのまま静かに別鍋にだしを移していく。目の前で繰り広げられる伊藤さんの流れるような所作は、まるでお茶のお点前を見ているかのようだ。おいしさを突き詰めた黄金の一滴には、まさに魂が入っている。

とある春の日のメニューから。『あわびと車海老の真丈』
こうしてとっただしを、伊藤さんは必ずゲストに一口飲んでもらう。それは、鰹節の余韻が長く続く香り、まろやかな旨みのだしの味を最初に味わってもらいたいから。そして、後に続く、椀物になったときの味の違いを感じてほしいからだ。
無垢なだしは、椀物として料理になると、自分の存在感を潜め、主となる素材の魅力をぐんと引き出し、そっと寄り添い、違う表情を見せる。
この日の椀種は、徳島のアワビと海老真丈。6時間蒸したというアワビは、歯をあてるとしっとりと柔らかく、素材そのものの塩味がほどよく中まで染み込んでいる。海老真丈は優しい甘さがあり、添えのうるいの苦味はいいアクセントだ。磯の香り、海老の香り、うるいのほろ苦い香りを、だしが一つにまとめて、調和する。素材の味が染み出し、だしは、どんどん春を湛えた味に変化していく。

スペシャリテの『金目鯛の炭火焼』箸休めの野菜の塩もみが添えられている
師匠譲りの妥協のなさで突き詰め、日本料理の技術を磨き、進化させ、自分なりに洗練させていく伊藤さんの手腕が発揮されているのは、むろん椀物だけではない。【炎水】という店名にもあるように、炭火焼きにもそのセンスが光る。
スペシャリテだという炭火で焼いた金目鯛の身は、香ばしい炭火の香りに包まれ、しっとり、ふっくらとした焼き上がり。対して皮は薄いガラスのような感覚を感じるほどパリッと焼き上げられている。
「金目鯛は、焼くのがとても難しい魚です。油断をするとあっという間に火が通ってしまい、ただの焼き物になってしまう。だから、金目鯛の肉汁が身の中でまだ"踊っている"うちに火からはずします。タタキと焼き物の中間のようなイメージですね。皮はパリッと仕上げたいから、皮の部分をすこし乾かすひと手間を加えて焼いています」と伊藤さん。
ちなみに、焼いた皮目を前にした独特の盛り付け方は、箸を入れたとき、皮目のパリンと割れるような感触を楽しんでほしい、という思いから。こうした、お客さまが食べるときの細部まで思いをめぐらし、心を砕く考え方は師匠の山本さんの教えが大きいという。

ボリュームたっぷりの締めのうなぎごはん。ゆくゆくランチができるようになったら、ランチでも出したいと構想中
そして、最後のクライマックスはごはんものでやってきた。全14品の食事の最後を飾るのは、ボリュームのあるうなぎ。"白ごはんといっしょに食べてほしいから"と、地焼きではなく、一度素焼きしたものを、蒸してから蒲焼きにしているという。
外側は香ばしく焼き上げているのに、中はふっくら。そのふっくらとした柔らかい身が、ごはんに溶け合うように馴染み、口のなかでやさしく混じり合う。
もうお腹いっぱい! と思っていたけれど、食欲を掻き立てる香りと軽やかな焼き方でするりとお腹におさまってしまうから不思議だ。

ミニマルかつ温かみのある木の内装。個室もあり
水菓子をいただいてお茶を飲みながら、その日のコース料理に思いを馳せる。奇をてらったものは一つもない。むしろシンプルなものばかりなのにまるで残像のように、それぞれの香りや食感や味が記憶に鮮明に残っている。
そんなことを考えていると、伊藤さんは最後にこう話してくれた。
「その瞬間にしかない香りを出すのが和食の真骨頂なんです。だからこそ、そこをお客さまに伝えたい。ピントが合うように"今、ここがおいしい"と感じる瞬間をとらえて時差なく届けたいんです。まだまだ道半ばですが、そこを考えて旬のおいしいものをお出ししていきたいですね」
この記事を作った人
撮影/佐藤顕子 取材・文/山路美佐
大学卒業後、丸の内の総合商社に入社するも食への探究心を抑えきれずイタリアに料理研修の旅へ。その後「家庭画報」ほかの雑誌で食・旅の編集を担当。ヒトサラ副編集長を経て、現在はフリーの食と旅の編集者に。美味探求の旅は30カ国以上にのぼる。
-

梅田/大阪駅食トレンド
大阪駅・梅田駅すぐ! 駅チカで楽しむ絶品ランチをいただけるお店5選|大阪
-

秋田/男鹿連載
ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~vol.4|秋田②
-

新宿・代々木グルメラボ
雨天でも安心! 新宿駅そばでアクセス抜群のおいしいお店|東京
-

富士吉田・富士五湖・山梨東部旅グルメ
大人のグルメ旅、富士山麓にある旅の途中で立ち寄りたい名店5選|山梨
-

渋谷グルメラボ
渋谷で1,000円台のランチが楽しめる、高コストパフォーマンスのお店|東京
-

恵比寿・代官山食トレンド
自家製で豆腐を手作りしながら豆腐の魅力を深掘り。おいしい、ヘルシー、楽しいがクセになる食堂酒場|【豆富食堂】恵比寿
-

恵比寿・代官山食トレンド
「俺の」シリーズ、11年ぶりに“和”の新業態が登場! 【俺の炉ばた 恵比寿】|恵比寿
-

銀座・有楽町グルメラボ
銀座・新橋エリアの駅近で優雅なホテルランチを楽しめるお店5選|東京
-

梅田・北新地旅グルメ
大阪駅近くで楽しむ絶品グルメ! 出張で大阪・梅田を訪れた後に立ち寄りたいお店5選|梅田
-

鎌倉・大船・逗子食トレンド
歴史ある鎌倉を散策したあとに立ち寄りたい、和食ランチが楽しめるお店5選|神奈川