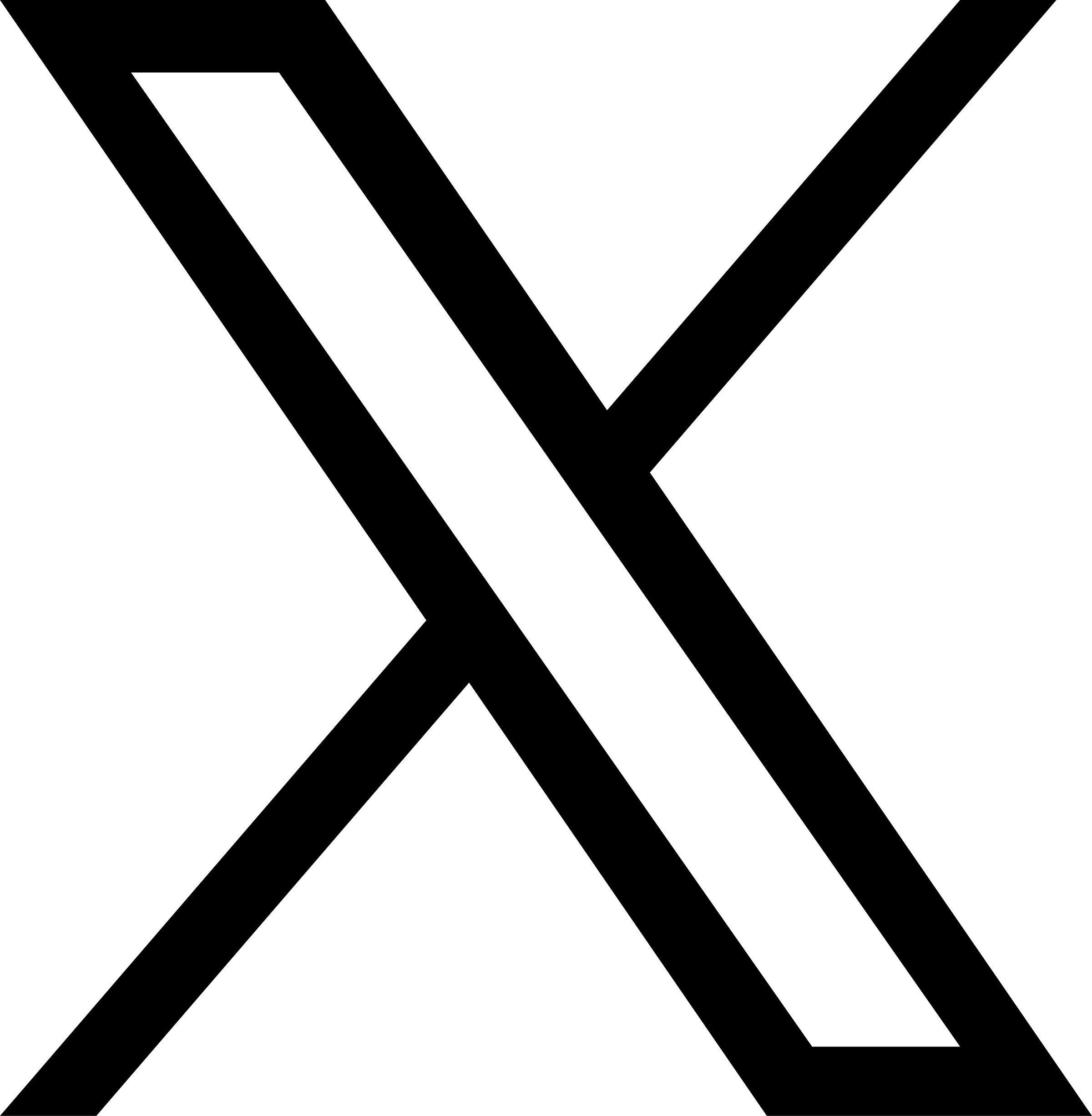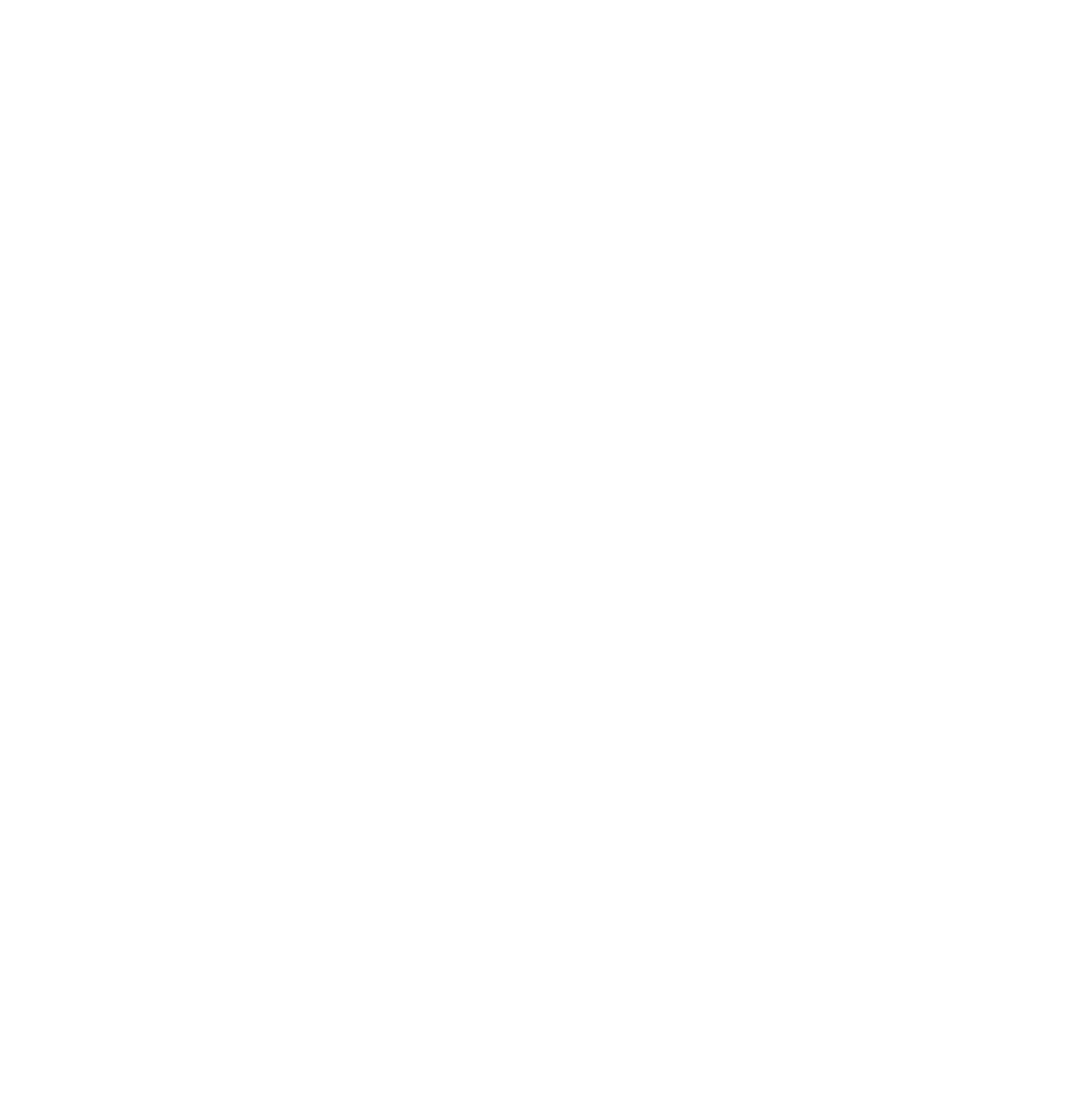<連載短編小説>#もう一度レストランで|「ピロシキ」白岩玄
恋人未満の二人をあとおしし、家族の記念日をともに祝い、おいしいお酒に友だちと笑う。レストランでのありふれた光景が、特別なものだったと気づいたこの数年。レストランは食事をするだけの場所ではなく、人と人とが交わり、人生が動く場所だった。これは、どこにでもあるレストランで起こる、そんな物語のひとつ。

「俺、最近、ロシア料理にはまってるんだよ」
店員が水と一緒に運んできたメニューを浮かない顔で開くなり、兄は笑顔でそう言った。三十五歳なのに未だに就職もせず、海外放浪を繰り返していた男からのランチの誘い。指定されたロシア料理の専門店であるこのレストランは、兄のお気に入りの店なのだそうだ。
店内は薄暗く、主な照明は各テーブルに吊られているランタンの形をしたペンダントライトだけだった。壁の棚にはキリル文字で書かれた本が並び、テーブルの上には赤と白のチェック柄のテーブルクロスが敷かれている。
正直なことを言えば、ロシア料理の店でランチをしないかと誘われたときから、あまり気乗りはしなかった。異国の料理がそこまで好きなわけではなかったし、ずっと現実から逃げて好きなことばかりしている兄に対して、あまりいい感情を持っていなかったからだ。それにラインの文面を見て気づいたのだが、その国の名前を聞くと、今は別のことが頭にちらついてしまう。でも、給料日前でお金がないし、兄がおごってくれると言うから、今回は付き合うことにした。
注文を済ませ、最初の料理が運ばれてくるまでのあいだに、兄は戦争の話をした。やっぱりその話題を出すのかと内心うんざりしたが、戦況を伝えるニュースを目にしない日はないから、ある程度は仕方がないのかもしれない。兄は歴史的な背景や、今後予想される展開についてひとしきり持論を述べたあとで、「やるせないよな」とかぶりを振った。自分はこの国の料理が心から好きだからこそ、痛ましい報道を目にするたびに、その気持ちまで否定されているような感じがすると言う。
「コロナで海外に行けなくなったのもそうだけどさ、なんかここのところ、しんどいことばっかりで。ほんと嫌になっちゃうよ」
気落ちしている兄に引っ張られたのか、私も近頃の自分の人生の停滞ぶりに思いを馳せざるを得なかった。一緒にしたら怒られるかもしれないが、もう一年近く婚活を続けてきて、さすがに疲れ果てていたからだ。どれだけアポを重ねてもいい結果につながらないし、ついこのあいだは、これまでで一番いいなと思っていた人に三回目のデートをドタキャンされて、そのまま音信不通になった。だから今日のテンションも恐ろしく低い。兄のおごりだと言うから来たけれど、もしここに来るまでのあいだに何かひとつでも落ち込むようなことがあったら、私はおそらくこの椅子に座っていなかっただろう。
嫌なことを思い出したせいで、まったく会話を楽しめないまま、時間だけが過ぎていく。まずまずだった前菜に続いて運ばれてきたのはピロシキだった。カレーパンに見た目が似ている、油で揚げた惣菜パンが、ケチャップと一緒に皿の上に載っている。
「あ、熱いから、気をつけてな」
取り上げようとした手を思わず離す。指で触れて確かめると、たしかに揚げたてで熱そうだった。紙ナプキンに包んだものを取り上げて、火傷しないように気をつけながらかぶりつく。口の中で熱さを慣らさなくてはならなかったが、表面がかりかりしている熱々のパンと、たっぷり入った具材の肉々しさの組み合わせが絶妙で、思わず「んー」と声が出た。
「うまいだろ?」
私は手で口を押さえながらうなずいた。共感してもらえたのが嬉しかったらしく、「俺もここのピロシキ大好きなんだよ」と笑っている。
「前は単に好きだったんだけどさ、最近はこれを食べるたびに、負けちゃダメだって思うんだよな」
どういう理屈でそう思うようになったのかが、まるでわからなくて理由を尋ねた。説明不足だったことに気づいた兄が、あぁ、と苦笑いをしながら手についたかすを払っている。
「この店のシェフがロシアの人なんだよ。この前、ちょっとだけ話したんだけど、今の状況にかなり心を痛めてるみたいでさ。でも、そんな中でも、こんなおいしいものを日々お客さんに作り続けてるわけだろ?」
カウンターの向こう側にいる年配のシェフに目を向ける。小さな鍋で作ったソースか何かを味見している白人の男性は、決して広くはないその厨房の中で手際良く動いて、自分の仕事に徹しているようだった。
「実は俺、今就活中でさ。全然雇ってもらえなくてメンタルがやられ気味なんだよ。海外放浪を始めたのも、新卒のときに就活でつまずいたからだっただろ? 当時のことをいろいろ思い出しちゃうんだよなぁ。なんでこんな、自分を無理やりプレゼンするようなことをしなくちゃいけないんだろうって」
兄が就活をしているのが驚きだったが、それ以上に、今彼が言ったのは、ここ最近の私が一番思っていたことだった。ある程度は仕方のないことだとわかっているが、本音を言えば、もっと無理せず自分のままで、相手との時間を積み重ねていくようなことがしたかったのだ。何よりも本来なら遠いのが当たり前なはずの「結婚」が、達成すべき目標になってしまうがゆえに、そこにちっとも辿り着けない自分がみじめに思えてしまうのがどうしようもなく嫌だった。
「でも、ここで食事をするたびに思うんだよ。つらくても、とにかく前を向いて、自分にできることをしようって」

目の前にある食べかけのピロシキが、シェフの想いを体現しているように思える。戦争の話にうんざりしたことや、ロシア料理と聞いただけで別のことがちらついてしまうなどと不満を持っていたことを反省した。今感じている申し訳なさを自分が変わるためのきっかけにしてもいいのなら、やるせなさに苦しみながらもできることをしようと頑張っている人たちを、私も少しは見習いたい。
「ごちそうさまでした。すっごくおいしかったです」
お勘定の際に厨房にいたシェフに声をかけると、彼は嬉しそうにはにかんで、片言の日本語でお礼を言った。きれいな青い瞳をした、笑顔のかわいい人だった。余計なお世話かもしれないけれど、心の中でエールを送る。祖国から離れたこの国で、複雑な想いを抱えながら頑張るあなたが、どうか少しでも穏やかな気持ちでいられますように。
「ありがとう。なんかちょっと元気出た」
店を出たあとで、私は兄にお礼を言った。ここに連れてきてもらわなかったら、きっと今でも狭い世界の中で自分に同情しているだけだっただろう。真昼の陽気の中に立っている兄は、どうして私が元気が出たのかわからなくて困惑しているようだった。
「あのさ、来月、またここで食事しない? 今度は私がおごるから」
兄との食事がすごく楽しかったわけではないけれど、思い切って誘ってみる。「マジで?」と目を丸くしている兄にうなずきながら、私も自分にできることをしようと思った。素朴で温かい料理を食べた余韻が、まだお腹に残っていた。
著者プロフィール
-

(撮影:小嶋淑子)
-
白岩玄 しらいわ・げん
作家。1983年京都府生まれ。
2004年「野ブタ。をプロデュース」で第41回文藝賞を受賞しデビュー。
同作は第132回芥川賞候補作となり、テレビドラマ化される。
他の著書に『ヒーロー!』『たてがみを捨てたライオンたち』など。

以前、豊橋市に住んでいたときによく行っていたお店です。
あっさりめの肉塩ラーメンと唐揚げの組み合わせが最高で、
今でも近くに寄った際は食べに行きます。
この記事を作った人
文/白岩 玄 イラスト/yasuna 構成/宿坊 アカリ(ヒトサラ編集部) 企画/郡司しう
-

釜石/大船渡/陸前高田旅グルメ 連載
ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~vol.2|岩手・宮城 三陸の漁師町の魅力 その①
-

富山県旅グルメ 連載
ヒトサラ編集長の食ダイアリー~とっておきの旅と食のはなし~vol.1|おいしい富山 その①
-
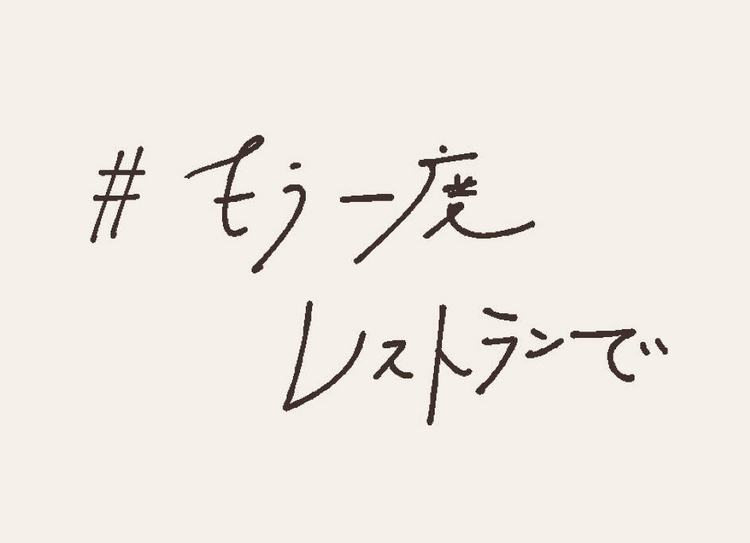
全国連載
<連載短編小説>#もう一度レストランで|「レストラン・オン・ザ・プラネット」白尾悠
-

東京都デート・会食
2人だけの特別な時間が過ごせる個室のあるお店5選|東京
-
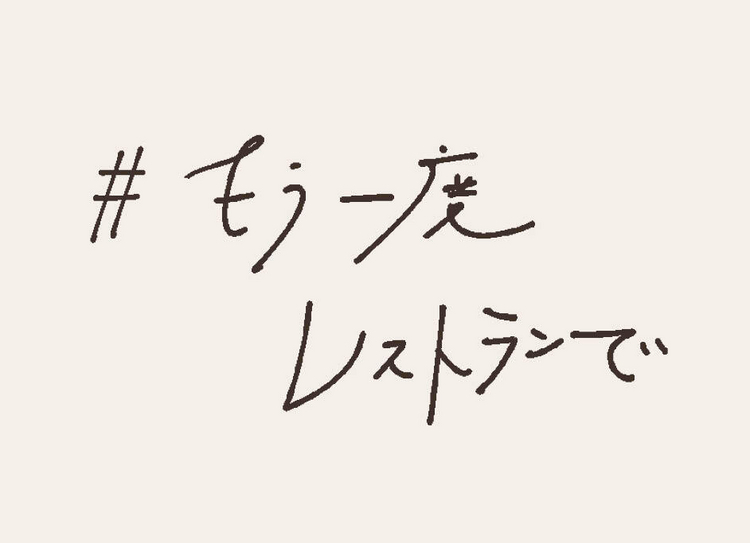
全国連載
<連載短編小説>#もう一度レストランで|「ダンゴにあう酒は」柚木麻子
-
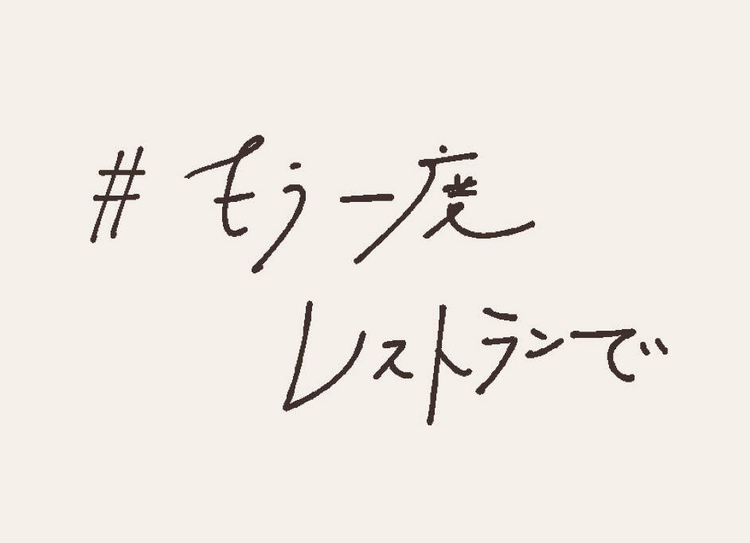
全国連載
<連載短編小説>#もう一度レストランで|「焼肉」宇垣美里
-
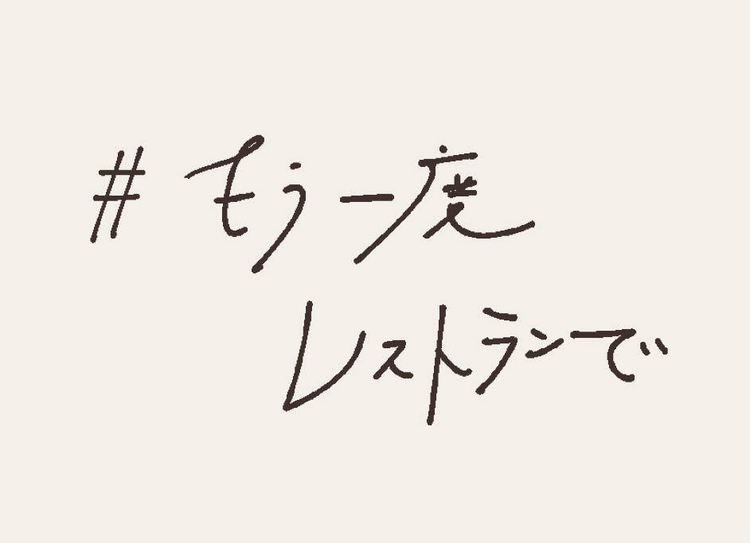
全国連載
<連載短編小説>#もう一度レストランで|「いわくとえにし」角田光代
-
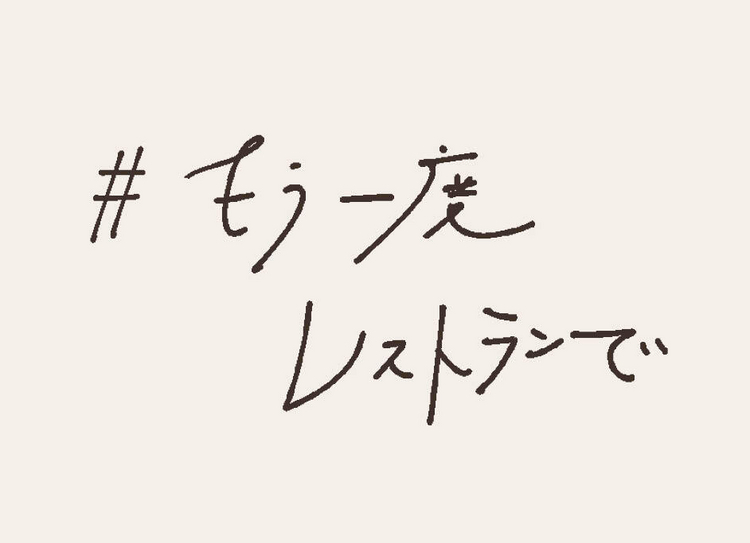
全国連載
<連載短編小説>#もう一度レストランで|「徒歩30分圏内の冒険」山崎ナオコーラ
-
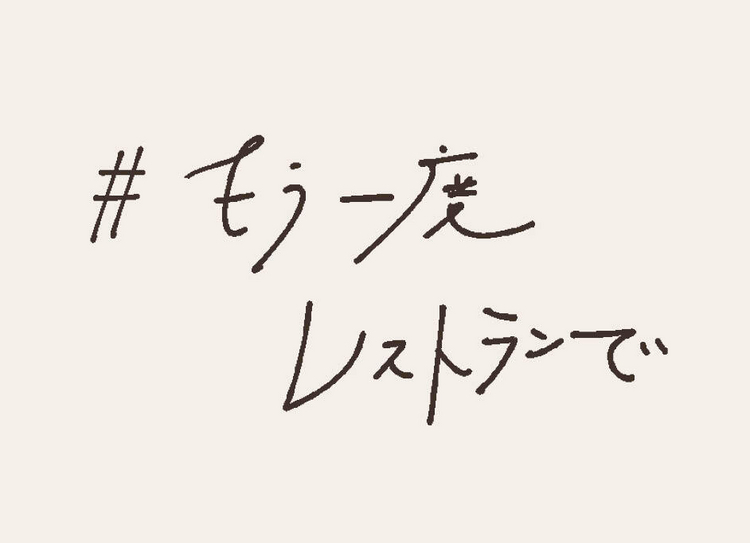
全国連載
<連載短編小説>#もう一度レストランで|「百円玉」中村航
-
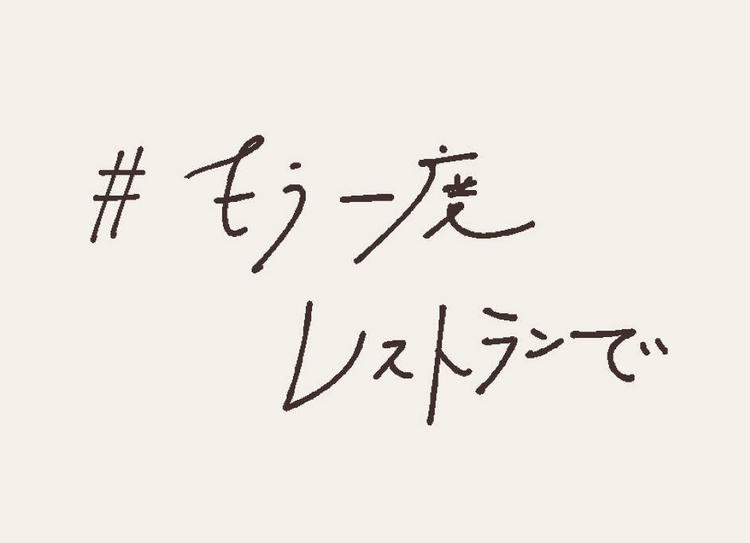
全国連載
<連載短編小説>#もう一度レストランで|「知らない食べ物」加藤千恵